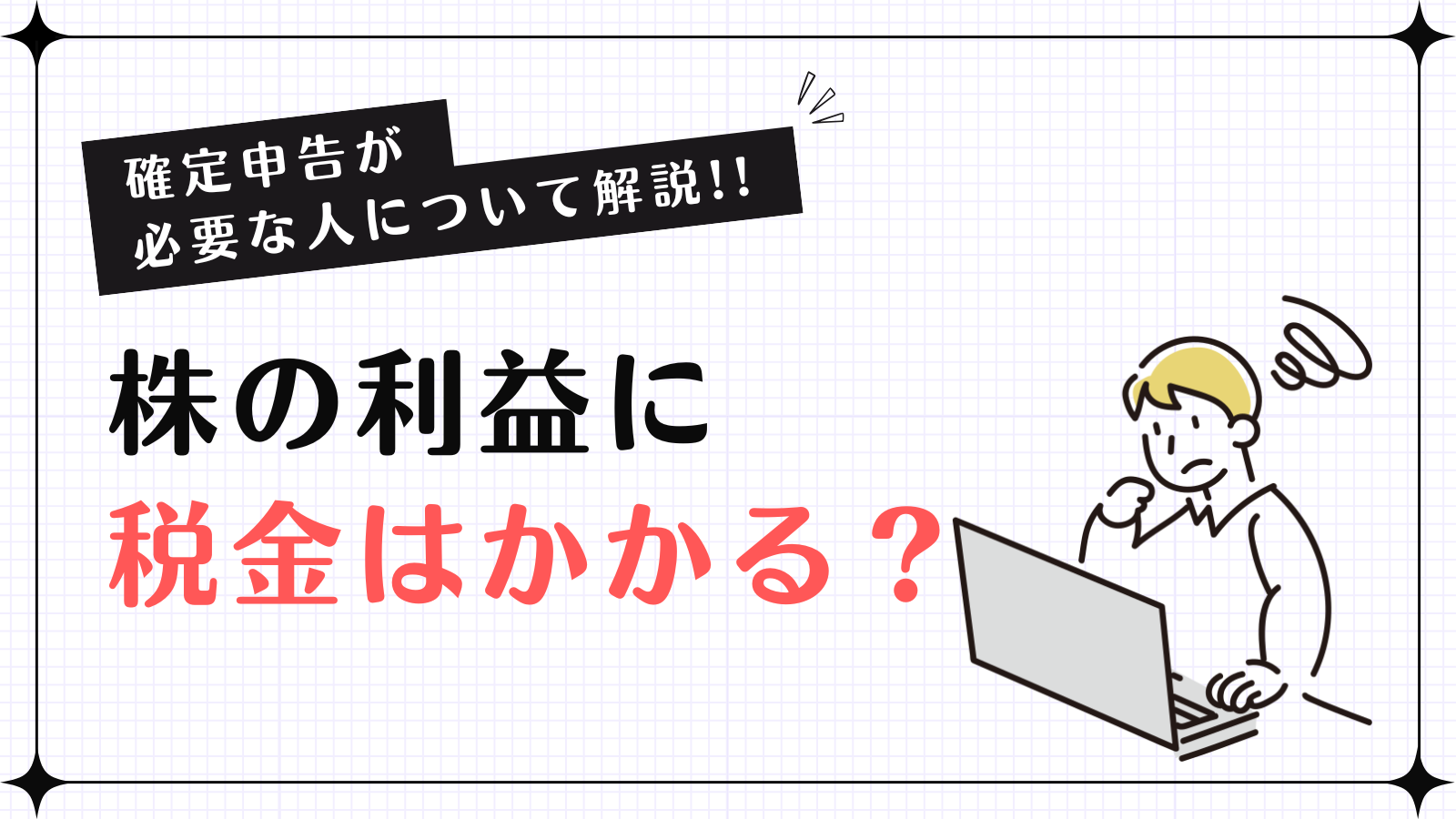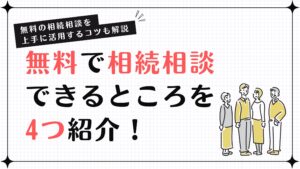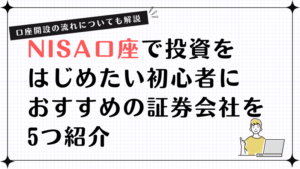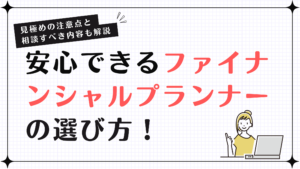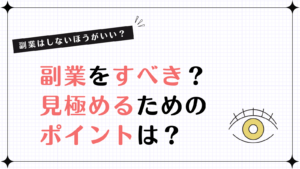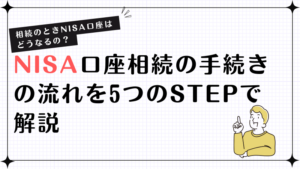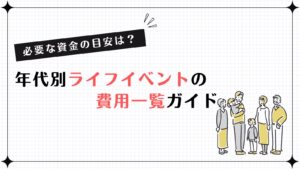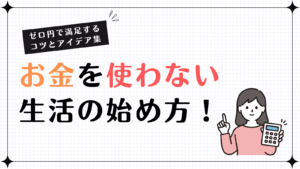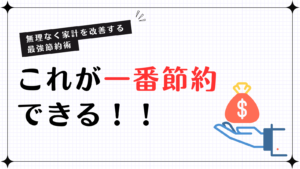「株の利益が少額だから税金は関係ないでしょ…」と思っていませんか?
株の売買益や配当には原則として税金がかかり、口座の種類や利益額によっては確定申告が必要になることもあります。
本記事では、いくら税金がかかるのか、いつ税金が発生するのか、申告が必要・不要になる代表ケースなどをやさしく解説します。
株取引を始める前に、ぜひ最後まで読んで、税金に関する知識を深めておきましょう。
株の利益には原則「20.315%」の税金
配当金や譲渡益など株の利益が発生した場合、20.315%の税金が発生します。
内訳は、所得税15%、住民税5%に加えて、2037年までは復興特別所得税(所得税の2.1%)が課税されるため。全部で15%+5%+0.315%=20.315%となります。
仮に配当金もしくは譲渡益が10万円発生した場合、23150円の税金がかかり、76850円が所得として残ります。
株で税金がかかるタイミング
株で税金がかかるタイミングは、下記のとおりです。
- 株を売却して利益が出た時
- 配当金を受け取った時
それぞれ解説していきます。
株を売却して利益が出た時
株を売却して利益が出た時に税金がかかります。
例えば、10万円の株を購入して11万円で売却した場合、売却利益額の1万円から所得額の20.315%(2031円)分を引いたものが所得となります。
配当金を受け取った時
配当金を受け取った時にも税金がかかります。
株の売却益と同じく税率は、20.315%です。
配当金は、口座への振込時に税率分を差し引きされた状態で入金されるので、自分で税額を計算したり納税の手続きを行ったりする必要がありません。
株の配当金はいつもらえる?受け取りまでの流れと調べ方を初心者向けに解説
株で利益が出た時の税金の納付方法
株で利益が出た時の税金の納付方法は、下記のとおりです。
- 確定申告をする
- 特定口座(源泉徴収あり)の場合、自動で引かれる
確定申告をする
確定申告をすることで株で利益が出た時の税金を納付することができます。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、税金を納める手続きです。
株の売買による利益だけでなく、他の所得と合算して計算をして税額を確定させます。
確定申告は、前の年の収入を、翌年2月16日から3月15日までの間に申告します。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、自動で引かれる
特定口座(源泉徴収あり)の場合、利益が確定した時点で税率分の金額が自動で徴収されるので、確定申告の必要がありません。
株式投資には、「一般口座」、「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3つがあり、確定申告の手続きが大変な方は、特定口座(源泉徴収あり)を選択するといいでしょう。
主婦が知っておくべきお得な証券口座開設の3つのポイントとは?
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は、下記のとおりです。
- 株式投資で利益が出ている
- 一般口座もしくは特定口座(源泉徴収なし)で取引をしている
株式投資で利益が出ている
一般的に株式投資で利益が出た場合、確定申告が必要となります。
しかし給与所得の有無や金額、株式投資の利益額によっては確定申告が不要な場合もあります。
ほかに所得がなく、株式投資の利益が48万円以下の人や給与所得が2000万円以下で株の利益が20万円以下の人は、確定申告の必要がありません。
一般口座もしくは特定口座(源泉徴収なし)で取引をしている
一般口座と特定口座(源泉徴収なし)で取引をしている人は、確定申告が必要となります。
一般口座を選択した場合、投資家本人が1年間の売買損益を計算して申告をしなければなりません。
一方、特定口座(源泉徴収なし)の場合、証券会社が発行する年間取引報告書に従って確定申告を行ないます。
副業として株式投資は稼げる?成功するための副業投資術を徹底解説
確定申告が不要な人
確定申告が不要な人は、下記のとおりです。
- 株で損失を出している
- 特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている
- NISAでのみ取引をしている
- 給与所得が0で株の利益が48万円以下
- 給与所得が2000万円以下で、株の利益が20万円以下
株で損失を出している
株取引をして損失を出した場合、確定申告の必要はありません。
しかし確定申告をすると税金が安くなる場合もあります。
特定口座(源泉徴収あり)で取引している
特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている人は確定申告は必要ありません。
特定口座(源泉徴収あり)以外の口座【一般口座および特定口座(源泉徴収あり)】で取引をして売却益が出た場合には、別途確定申告が必要となります。
NISA口座でのみ取引している
NISAのみで株式を購入している場合、確定申告は不要です。
NISAは、非課税口座なので、NISA口座を使って取引をして利益が出ても税金はかかりません。
他に所得がなく株の利益が48万円以下
他に所得がなく、株の利益が48万円以下の人は、確定申告が必要ありません。
特定口座(源泉徴収あり)で取引を行なっており、源泉徴収をされた場合には、確定申告をすることで徴収された税額が還付されます。
給与所得が2000万円以下で、株の利益が20万円以下
1箇所からもらっている給与所得を受けている人で給与所得が2000万円以下で、給与所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告が必要ありません。
NISA口座開設後に放置するとどうなる?【日本証券業協会のNISA相談コールセンターに聞いてみた】
特定口座(源泉徴収あり)での取引が安心
株式投資をするなら特定口座(源泉徴収あり)での取引が安心です。
投資で得た利益を証券会社が計算して、自動で税金を収めてくれるので確定申告の手間を省くことができます。
仮に損失が出たとしても確定申告をすれば、余分に徴収された税金が還付されるので安心して利用することができます。
株の利益を節税する方法
株の利益を節税する方法は、下記のとおりです。
- NISAを活用する
- 繰越控除と損益通算を活用する
NISAを活用する
NISAは、投資を通じた資産形成を促すために国が設けた「非課税制度」です。
通常かかる20.315%の税金がかからないため、長期投資に向いています。
また、NISAには、成長投資枠とつみたて投資枠の2つの枠があります。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 投資期間 | 無期限 | 無期限 |
| 年間投資枠 | 240万円/年 | 120万円/年 |
| 非課税保有限度額 | 1200万円(つみたて投資枠と合わせて1800万円) | 1800万円 |
| 投資対象 | 上場株式・投資信託など | 長期積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
| 譲渡益に対する課税 | 非課税 | 非課税 |
| 購入方法 | 一括・積立 | 積立のみ |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
成長投資枠とつみたて投資枠では、年間投資枠と非課税保有限度、投資対象が異なります。
まず年間の投資枠についてですが、成長投資枠は、年間240万円に対して、つみたて投資枠は年間120万円までで併用すると360万円まで金融商品を購入することができます。
成長投資枠は1200万円まで、つみたて投資枠と成長投資枠あわせて最大1800万円まで非課税で株や投資信託を購入することができます。
成長投資枠とつみたて投資枠は、投資できる金融商品が異なり、成長投資枠は、上場株式や当信託、つみたて投資枠は、長期積立や分散投資に適した投資信託を購入することができます。
【新NISAとは?】知識0の方でも理解できる新NISA完全ガイド
繰越控除と損益通算の制度を活用する
繰越控除と損益通算の制度を活用することで節税をすることができます。
繰越控除とは?
繰越控除は、株の売買で出た損失を翌年以降の3年間にわたって繰り越すことができる制度です。
株取引で損失を出した場合、翌3年間いっぱいは利益と相殺することが可能なので、相殺分は課税されません。
繰越控除の制度を利用するためには、繰越す年と翌3年間は確定申告が必要となります。
損益通算とは?
損益通算は、その年の株取引の損失を配当所得と相殺できる制度です。
仮に100万円の損失を出して、10万円の配当所得を得ていたら、10万円分の配当所得に課税されていた金額がもどってきます。
この場合、20,315円が戻ってきます。
受け取る配当金の金額に応じて課税方式を選択する
受け取る配当金の金額に応じて課税方式を選択すると節税することができます。
一般的に上場株式などの配当金は、支払われる際に所得税などが源泉徴収をされるため確定申告が不要となりますが、場合によっては申告をした方が有利になる場合があります。
その際、以下の2つの方式から選択することができます。
- 総合課税
- 申告分離税
総合課税
総合課税は、課税所得を計算するときに、納税者の所得を合算して計算し、税額を出す方式です。
上場株式の配当金の場合、総合課税を選択すると配当控除を受けることができます。
課税総所得の合計金額が1000万円以下の場合、10%の配当控除をを受けることができます。(1000万円を越える場合には、5%)
課税所得が1000万円以下の場合には、下記の方法で配当控除額を算出することができます。
【課税総所得が1000万円以下の場合の配当控除額の算出方法】
配当総所得×10%
例)課税所得が600万円で配当総所得が25万円の場合
25万円×10%=2.5
配当控除額は、25,000円
課税総所得が1000万を越えた場合の配当控除額の算出方法は、下記の番号順に行なうと算出できます。
【課税所得が1000万円を超えた場合の配当控除額の算出方法】
- 配当総所得-(課税総所得-1000万円)
- 配当総所得-①
- 配当控除額=①×10%+②×5%
例)課税所得1025万円、配当所得50万円の場合
50万円-(1025万円-1000万円)=25万円
50万円-25万円=25万円
25万円×0.1+25万円×0.05=3.75
配当控除額は、37,500円
申告分離課税
申告分離課税は、特定の収益や所得を一般的な所得と合算せず別々に課税をする方式です。
申告分離課税を選択することで、株の売買で損失を出した場合に売却損と配当所得で損益を通算することができます。
その結果、配当所得がマイナスになった場合、減った配当所得分の税額がもどってきます。
仮に総所得が1000万円以下で、配当が80万円で40万の損失を出した場合、40万円分の税額だけですみます。
【80万円の場合】
80万円×20.135%=162,520円(所得税・住民税)
【40万円の場合】
40万円×20.315%=81,260円(所得税・住民税)
よくある疑問Q&A
Q1. 株の利益には必ず税金がかかるのですか?
A. はい、原則として株の売却益や配当金には20.315%の税金がかかります。
ただし、NISA口座を利用していれば、一定の投資額までの利益や配当は非課税になります。
Q2. NISA口座を使えば確定申告は不要ですか?
A. はい、NISA口座での取引はすべて非課税扱いなので、確定申告は不要です。
ただし、NISA口座と通常の口座(特定・一般口座)を併用している場合は、通常口座での取引分のみ申告が必要になることがあります。
Q3. 株の利益が少額でも確定申告は必要ですか?
A. 以下の条件にあてはまる場合は申告不要です。
-
他に所得がなく、株の利益が48万円以下
-
給与所得が2,000万円以下で、株の利益が20万円以下
-
特定口座(源泉徴収あり)を利用している
それ以外の方は、利益額に応じて確定申告が必要になります。
Q4. 株で損をした場合も確定申告をした方がいいですか?
A. はい。損失を申告すると翌年以降の節税につながることがあります。
確定申告をすれば、「損益通算」や「繰越控除」の制度を使って、3年間利益と損失を相殺できるため、結果的に税金を減らすことが可能です。
Q5. 株の税金は会社にバレますか?
A. 「特定口座(源泉徴収あり)」で運用していれば、基本的に勤務先に通知されることはありません。
ただし、確定申告を行う場合や副業扱いになる場合は、住民税の申告により会社へ情報が伝わる可能性があります。
まとめ
株で得た利益には、原則として20.315%の税金がかかります。
課税されるのは「株を売って利益が出たとき」や「配当金を受け取ったとき」などです。
ただし、NISA口座を利用すれば非課税で運用できます。
売却益や配当金がそのまま手元に残るので、初心者にとっても大きなメリットです。
一方で、NISAでは損益通算や損失の繰越はできないため、短期売買には向いていません。
株式投資を始める際は、まず次の3点を意識しましょう。
-
特定口座(源泉徴収あり)を選ぶ → 税金が自動で処理され、確定申告の手間がない
-
NISA口座を活用する → 利益を非課税で積み上げられる
-
損益通算や繰越控除を理解する → 無駄な税金を減らすチャンスになる
株の税金は「難しそう」と感じるかもしれませんが、仕組みを一度理解すれば怖くありません。
制度を正しく使い分けながら、ムリなく・ムダなく・安心して投資を続けることが大切です。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。