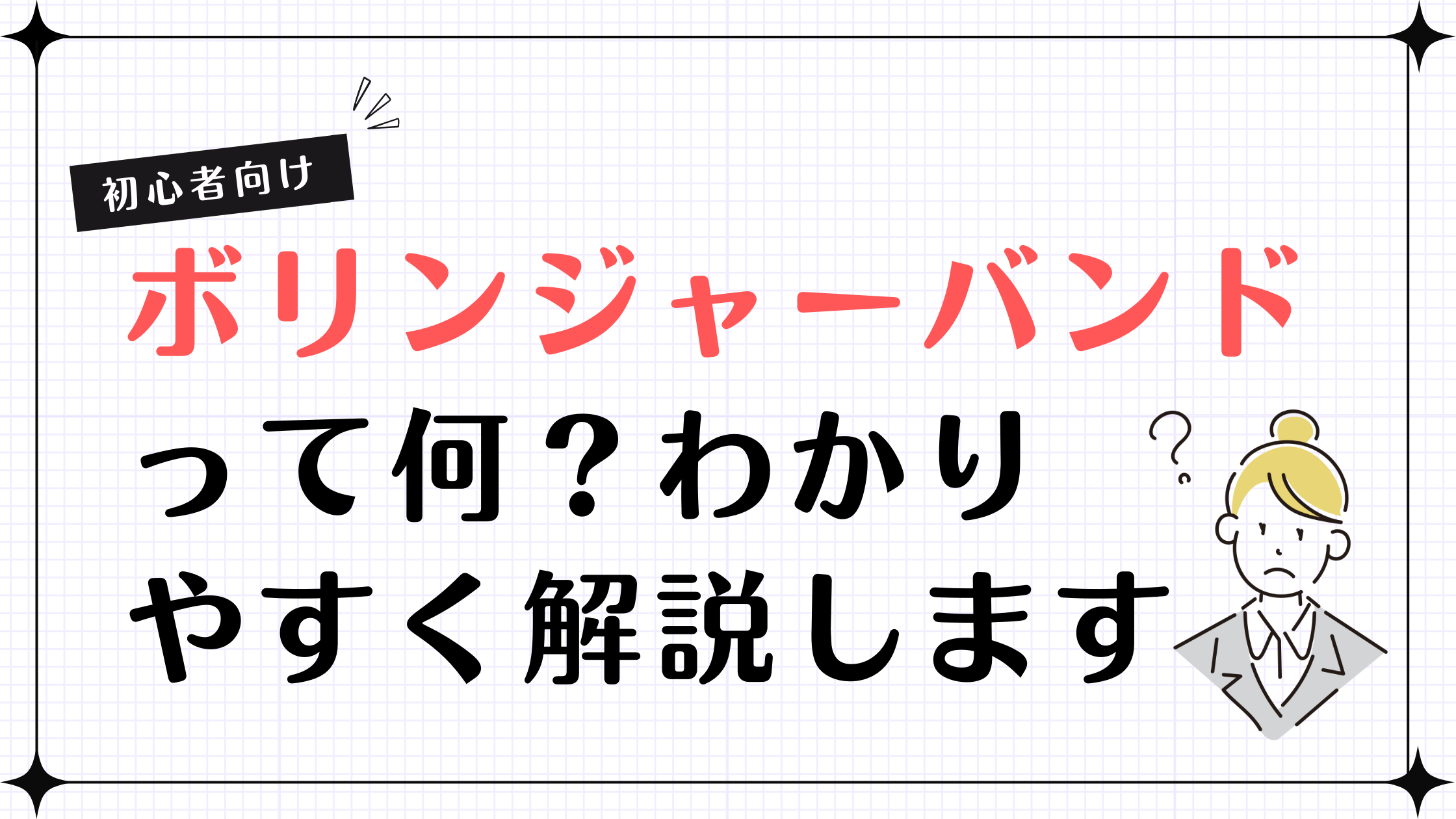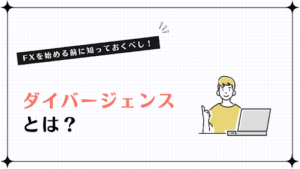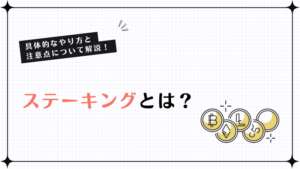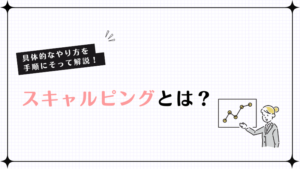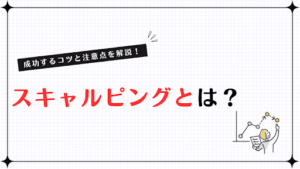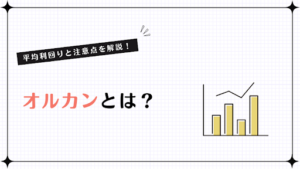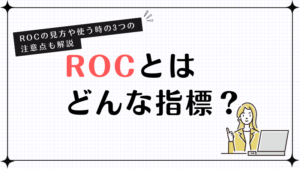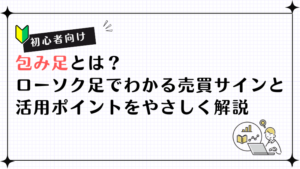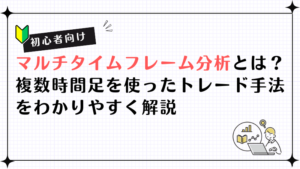ボリンジャーバンドという言葉を聞いたことはありますか?
株やFXなどのテクニカル分析で非常によく使われる指標のひとつで、「今の株価が高いのか・安いのか」を一目で判断できる“相場の温度計”のような役割を果たします。
「難しそう」と感じる方も多いですが、ボリンジャーバンドは“統計学”をもとに作られたシンプルな仕組みです。
初心者でも使い方を理解すれば、トレンドの勢いや反転のタイミングをつかむことができるようになります。
本記事では、ボリンジャーバンドの意味と仕組みや初心者が注意すべきポイントなど、わかりやすく解説します。
ボリンジャーバンドって何?

(図1 ボリンジャーバンドと株価)
ボリンジャーバンドは、1980年代にアメリカの投資家ジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル指標です。
株価が「平均(移動平均線)」からどのくらい離れて動いているか(乖離)を統計的に可視化したもので、価格の勢いや反転の目安として使われます。
株価の勢いの変化や反転の目安・方向を見るための指標です。
図1のように、標準偏差(=σ{シグマ})は±1σ(緑と青の線)、±2σ(茶色と赤の線)、±3σ(黄色とオレンジの線)のバンド(幅)がありそれぞれ、約68%、約95%、約99%の確率で収まるとされています。
つまり、株価が+1σに近づくと約68%の確率で値動きはその範囲内に収まるということです。
ちなみに、株価が±2σに達すると約95%という高い確率で範囲内に収まることから、±2σを意識しているトレーダーが多いと考えられます。
このようにボリンジャーバンドは、相場の過去の平均から現在の価格がどれぐらい離れているかを標準偏差として表して、ボラティリティ(価格変動)のレンジ(範囲)が簡単に分かるように工夫されています。
バンドウォークとは?順張りで利益を出せるようになる見極め方を解説
ボリンジャーバンドの特徴と使い方
ボリンジャーバンドの最大の特徴は、「統計的に裏づけられた価格のバランス」が見える点です。
たとえば、株価が-2σラインまで下がった場合は「売られすぎ」と判断され、反発上昇のサインになることがあります。
逆に、+2σを超えた場合は「買われすぎ」とみなされることが多いです。
この考え方を応用したのが、逆張り手法です。
ただし、強い上昇・下降トレンドでは、株価がバンドに張りついたまま動くことがあります。
この現象を「バンドウォーク」と呼び、順張りのエントリーチャンスとしても利用されます。
ボリンジャーバンドの最強手法!利益につながる最強設定や組み合わせを徹底解説
ボリンジャーバンドの活用とメリット・デメリット
ボリンジャーバンドは逆張りで使われることが一般的です。
例えば、マーケットが-1σ~-3σに近付いた時は買いのサインとして用いられています。
また、マーケットが1σ~3σに近付いた時に売りのサインとして用いられています。
(ちなみに「逆張り」とは、株価が下がっている(上がっている)ときに買う(売る)という手法です。)
このように、一目でマーケット状況を判断できることがボリンジャーバンドのメリットですが、一方でデメリットもあります。
それが、株価が必ずσ内に収まるわけではないということです。
例えば、横ばいのバンドが続いた後に株価が急激に動き出し、+1σや+2σを超えた後にさらに株価が上昇することがあります。
これは横ばいであった株価がその間にエネルギーを溜めて一気に動き出す(ブレイクアウト)という理由から起こります。
つまり、株価が+3σを超える可能性もあります。
このようにボリンジャーバンドの±2σのラインに沿いながら強い上昇や下落を伴う動きをバンドウォークと呼びます。
σ内に収まる確率を信じすぎると株価予測を誤る原因になるので注意が必要です。
多くのプロトレーダーは他のテクニカル指標を組み合わせて使うことでこのような弱点を補っています。
初心者におすすめの設定
初心者の方は、まず次の設定でチャートを表示してみましょう。
-
期間:20日移動平均線
-
偏差(σ):2
この「20日+±2σ」は最も標準的な設定で、約1か月の値動きのバランスを見ることができます。
短期トレードでは「10日+±1σ」、中長期投資では「50日+±2σ」など、目的に応じて調整しましょう。
よくある疑問Q&A:ボリンジャーバンドの正しい使い方
Q1. ボリンジャーバンドはどの期間設定がベスト?
A. 標準的には「20日移動平均+±2σ」が最もよく使われます。
20日というのはおおよそ1か月の取引日数に相当し、短期・中期のトレンドをバランスよく捉えられるためです。
ただし、デイトレードなど短期取引では「10日+±1σ」など、より短い期間で感度を上げる設定も有効です。
自分のトレードスタイル(短期・中期・長期)に合わせて期間を調整しましょう。
Q2. バンドの「拡大」と「収縮」はどう見ればいい?
A. ボリンジャーバンドは「相場の温度計」とも言えます。
バンドが広がる(拡大)ときは相場が活発で、トレンドが発生しているサインです。
逆にバンドが狭くなる(収縮)ときは、相場が落ち着き方向感がない状態を意味します。
多くのトレーダーは「収縮後の拡大」に注目しており、ブレイクアウト(急上昇・急落)の前兆として活用します。
Q3. ボリンジャーバンドは株だけ?
A. いいえ。
FXや仮想通貨など、値動きのある金融商品ならほとんどで利用できます。
Q4.どのタイミングで売買すればいい?
A. ±2σ付近での反発を狙う逆張りが基本です。
ただし、強いトレンドでは“逆らわない”ようにしましょう。
まとめ
ボリンジャーバンドは、価格の勢いや反転ポイントを“確率”で判断できるテクニカル指標です。
移動平均線と標準偏差を使うことで、「今の株価が高いのか安いのか」を視覚的に判断できます。
-
±2σの範囲で、約95%の確率で価格が収まる
-
バンドが広がる=相場が活発(トレンド発生)
-
バンドが狭まる=相場が静か(方向感がない)
このように、ボリンジャーバンドは“相場の温度”を測るツールとして非常に有効です。
初心者の方は、まず「20日移動平均+±2σ」の標準設定でチャートを見てみましょう。
実際にチャートを動かしながら観察することで、相場の流れを“体感で”つかむ力が身につきます。
ただし、ボリンジャーバンドは単体では完璧な指標ではありません。
RSIや移動平均線など、他のテクニカル指標と組み合わせることで精度を高めることができます。
相場は「確率の世界」です。
ボリンジャーバンドを理解すれば、感情ではなくデータに基づいて判断できるようになります。

著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。
地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。
その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。