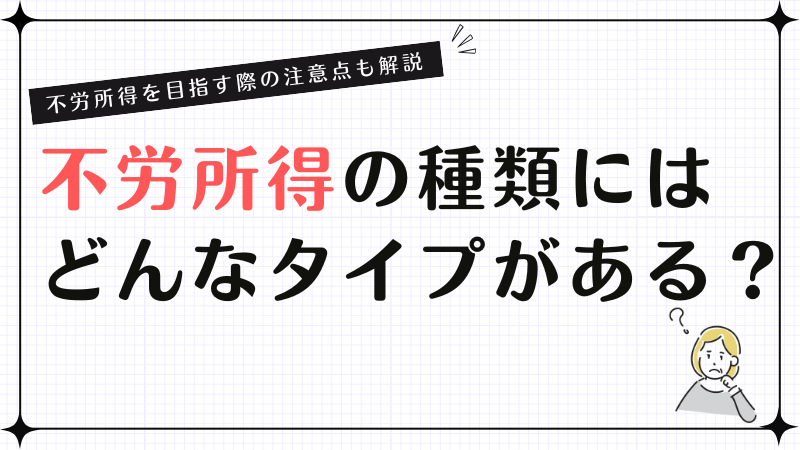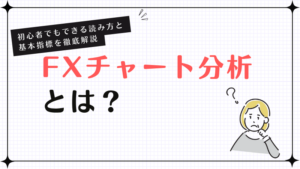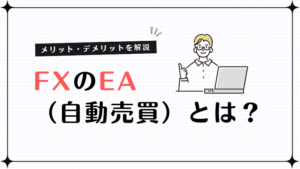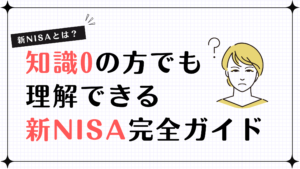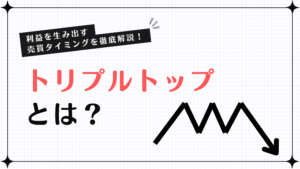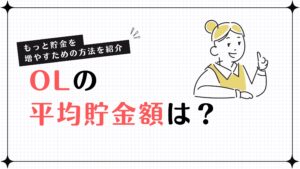「不労所得にはどのような種類があるの?」と疑問に思っていませんか?
投資や副業を検討している方にとって、不労所得は魅力的な収入源であると考えている一方、具体的にどのような方法があるのかわからないという方が多いようです。
そこで今回は、不労所得の基本的な種類について詳しく解説します。
また、不労所得を目指す際の注意点についてもまとめました。
ぜひ、本記事の内容を参考に、ご自身でも経済的自由を目指すための第一歩として不労所得への投資を検討してみてください。
不労所得で自由な生活を実現する方法!一生役立つ技術を手に入れるには?
不労所得の種類
不労所得には大きく分けて以下の4つのタイプがあり、それぞれ初期コストや収益化までの時間が異なります。
- 金融資産型
- 不動産収入型
- デジタル型
- 権利型
本章では、各タイプにどのような方法があるかについて詳しく解説していきます。
なお、各タイプの初期コストと収益化までの時間は以下のようになります。
| 種類 | 初期コスト | 収益化までの時間 | 主な具体例 |
| 金融資産型 | 中~高(数十万円~数千万円) | 数ヶ月~(配当金や利息受け取りまで) | 株式投資・債券投資など |
| 不動産収入型 | 高(数百万円~数千万円) | 数ヶ月~数年(賃貸開始まで) | 家賃収入・駐車場経営など |
| デジタル型 | 低~中(数千円~数十万円) | 半年~数年(サイト育成など) | ブログ、YouTubeなど |
| 権利型 | 低~中(制作コスト) | 数ヶ月~数年(販売まで) | 印税・ライセンス収入など |
ここからは、それぞれのタイプの具体的な方法について深掘りします。
金融資産型
本章で紹介する金融資産型の不労所得を得るための手段は、以下のとおりです。
- 配当金
- 債券
- REIT
それぞれみていきましょう。
配当金
配当金は株式に投資して得られる代表的な不労所得であり、投資初心者でも比較的はじめやすい方法です。
会社が事業で得た利益の一部を株主に還元する制度で、保有している株式数に応じて定期的に配当金が支払われます。
たとえば、年間配当利回り3%の株式を1,000万円分保有していれば、年間30万円の配当金を手に入れることが可能です。
多くの企業では年2回に分けて支払われるため、半年ごとに収入が入る安定感があります。
配当金投資の魅力は、株価の変動に関係なく定期的な収入が期待できる点です。
ただし、業績悪化により配当金が減額されたり無配になったりするリスクもあるため、複数の優良企業に分散投資をするのが重要です。
債券で利息を得る
債券投資は、国や企業にお金を貸すと定期的に利息収入が得られる安定性の高い手段です。
債券とは借用証書のようなもので、お金を貸す代わりに約束された利息が定期的に支払われる仕組みになっています。
個人向け国債の場合、固定3年・固定5年・変動10年の3つのタイプがあり、半年ごとに利息が受け取れます。
国債は国が発行するため、企業が発行する社債と比較して安全性が高く、投資初心者にも適した商品です。
ただし、早期解約時にはすでに受け取った直近2回分の利子相当額が差し引かれるので、あらかじめ投資計画をたててから購入するのが大切です。
REIT
REIT(リート)とは、証券化された不動産に投資する投資信託であり、不動産の賃貸収入や売却益を原資とした分配金を受け取れる商品です。
多くの投資家から集めた資金でオフィスビル・商業施設・ホテルなどの不動産物件を購入・運用するため、個人では投資困難な大型物件にも少額から参加できます。
REITの分配金は一般的に年2回の頻度で支払われる場合が多く、国内REITの配当利回りは銘柄によって異なりますが、おおむね年3%〜5%前後が目安となります。
REITの最大のメリットは、数万円という少額から不動産投資をはじめられる点です。
実際に不動産を購入する場合と異なり、プロの運用会社が代行してくれるため不労所得に近い仕組みといえます。
不動産収入型
不動産収入型の初期コストは高額ですが、比較的安定した収入を得やすいのが特徴です。
本章で紹介する不動産収入型の不労所得を得るための手段は、以下のとおりです。
- 家賃収入
- 駐車場経営
それぞれ解説します。
家賃収入
家賃収入は、マンションやアパートを所有し、賃貸して毎月安定した収入を得る不労所得です。
入居者がいる限り毎月決まった日に家賃が振り込まれる仕組みで、不労所得に適した方法として人気があります。
たとえば、月額家賃8万円の物件を3戸所有していれば、満室時には月24万円の家賃収入が得られます。
管理会社に物件管理を委託すれば、入居者対応や建物メンテナンスなどの手間を大幅に削減でき、より不労所得に近づけさせることが可能です。
家賃収入の魅力は、一度入居者が決まれば長期間にわたって継続的な収入が見込める安定性にあります。
ただし空室リスクや修繕費用、管理費用などの経費も発生するため、立地選びや物件選定には十分な調査と検討が必要です。
駐車場経営
駐車場経営は、土地活用による不労所得の中でも比較的はじめやすく、管理の手間が少ない方法です。
初期投資が他の不動産投資と比較して安く、機械設置による無人化も可能なため、本業が忙しい人でも取り組みやすい特徴があります。
駐車場には月極駐車場とコインパーキングの2種類があり、住宅地では月極駐車場、商業地域やオフィス街ではコインパーキングが適している傾向があります。
なお、駐車場経営の運営では立地条件が収益性に大きく影響するため、事前の需要調査や収益シミュレーションが必須です。
土地を有効活用して安定した不労所得を得たい場合、駐車場経営は検討に値する選択肢の一つです。
デジタル型
デジタル型は初期費用を抑えられますが、集客やコンテンツ制作などに時間と労力がかかり、安定収益まで長期戦になりやすい特徴があります。
本章で紹介するデジタル型の不労所得を得るための手段は、以下のとおりです。
- ブログ
- YouTube
それぞれ解説します。
ブログ
ブログ運営では、自分で記事を書いて広告収入やアフィリエイト収入が自動的に発生する仕組みを構築して不労所得を得ることが可能です。
記事の閲覧数や広告のクリック数、商品購入などの成果に応じて報酬が支払われるため、良質なコンテンツを継続的に作成すれば長期的な収益が見込めます。
ブログの最大の魅力は、初期費用がほとんどかからず誰でもはじめられる点です。
ただし、検索エンジンで上位表示されるまでには時間がかかり、収益化までには相当な努力と継続が必要になります。
初心者の方がブログで不労所得を目指す場合、自分の得意分野や経験を活かした専門性の高いコンテンツ作りからはじめるのがよいでしょう。
YouTube
YouTubeでは、作成した動画コンテンツを視聴者にみてもらい広告収入を得ることで不労所得を実現できる現代的な手法です。
一度作成・投稿した動画は24時間YouTube上で再生され続け、視聴されるたびに広告報酬が発生します。
収益源は広告だけでなく、動画説明欄でのアフィリエイトや自社商品販売も可能です。
YouTubeで稼ぐ最大の強みは、一度作成した動画コンテンツが長期間にわたって収入を生み続ける点です。
人気動画になれば数年後でも再生され続け、都度収益が発生します。
ただし、収益化の条件を満たすまでに時間がかかり、継続的なコンテンツ制作と視聴者との関係構築が不可欠です。
権利型
権利型は、作成したコンテンツや権利から継続的に収入を得られる仕組みで、一度仕組みが構築できれば長期で収益化が可能です。
本章で紹介する権利型の不労所得を得るための手段は、以下のとおりです。
- 印税
- ライセンス収入
それぞれみていきましょう。
印税
印税収入は、一度コンテンツを作成すれば継続的に自動で収入が得られる不労所得です。
出版した本や電子書籍が売れたり読まれたりするたび、著者に一定割合の報酬が自動的に支払われる仕組みになっています。
現在では電子書籍の出版が手軽になり、Amazon Kindleでの個人出版も可能です。
Kindle出版では販売ごとの印税に加えて、Kindle Unlimitedで読まれたページ数に応じた報酬も得られます。
紙の書籍の場合は出版社を通じた一般出版で、通常は売上の10%程度が印税として支払われます。
印税の魅力は、一度いいコンテンツを作れば長期間にわたって収益が続く点です。
ベストセラーになれば数年から数十年にわたって印税収入が期待できます。
ただし、読者に価値を提供できる質の高いコンテンツを作るには、専門知識や文章力、マーケティングスキルが必要になります。
ライセンス収入
ライセンス収入は、自身が持つ知的財産を他社や第三者に使用許可を与えると得られる不労所得です。
特許・著作権・商標などの知的財産権を活用し、自分で事業化しなくても安定的な収入を生み出せる仕組みです。
具体的には、特許権を取得して企業に技術利用のライセンスを与え、使用料やロイヤリティを受け取る方法があります。
また、キャラクターやブランドの商標権、音楽や画像の著作権なども、使用許可の対価として継続的な収入源になります。
ライセンス収入では「知的財産を使わせて稼ぐ」という発想で、自分が直接労働しなくても他者の事業活動を通じて収益を得ることが可能です。
ただし、価値のある知的財産を生み出すには高度な専門知識や創造力が必要で、権利の取得や管理にも相応のコストがかかります。
初心者がお金の勉強を始めるなら?失敗しないためのステップとコツ
不労所得を目指す際の注意点
不労所得を目指す際に気をつけておくべき注意点は、以下の3つです。
- 詐欺被害に注意
- 不労所得になるまでに労力がかかる
- 勤務先の就業規則をチェックする
それぞれみていきましょう。
詐欺被害に注意
不労所得を目指す際は、詐欺被害への細心の注意が不可欠です。
なぜなら、投資初心者や知識不足の人を狙った、悪質な詐欺案件も少なからず存在しているからです。
たとえば「確実に月利10%以上の利益が出る」といった非現実的な高利回りを謳う投資商品などが挙げられます。
また、オンラインサロンやセミナー形式の投資勧誘で、高額な初期投資を求められたりする場合も要注意です。
そのため、うまい話には必ず裏があることを念頭に置き、信頼できる情報源を元に十分な調査を行って投資判断を下すのが賢明です。
不労所得になるまでに労力がかかる
不労所得という名称から「楽に稼げる」というイメージを持ちやすいですが、実際には安定した収入を得る仕組みを構築するまでに想像以上の労力と時間が必要です。
どの手法を選んでも、最初の準備段階では相当な努力が求められます。
株式投資や不動産投資をはじめる場合、まず投資資金の準備や市場調査・物件選定・運用方法の学習などに多くの時間を費やさなければなりません。
ブログやYouTubeの場合は、サイト構築・コンテンツ作成など、成果が出るまでに数ヶ月から数年の地道な作業が必要です。
「不労」とは仕組みが完成した後の状態であり、不労所得を得るまでに相当な準備が不可欠であることを理解して取り組まなければいけません。
そのため、不労所得を実現させるには計画を事前に立てて、長期的な目線で行動するのが重要です。
勤務先の就業規則をチェックする
不労所得を狙う前に、勤務先の就業規則を確認し、副業や投資活動に関する規定を把握しておくのが重要です。
会社によっては副業が制限されている場合があり、不労所得を目指していると就業規則違反になるリスクがあります。
近年は副業を解禁する企業が増えていますが、本業への支障となる活動の制限や事前申請などの条件が設けられている場合があります。
また、公務員の場合は法律により副業が厳しく制限されているため特に注意が必要です。
就業規則違反が発覚した場合、戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇といった重大な処分を受ける可能性があります。
不労所得を目指す際は、事前に人事担当者や上司に相談し、会社の方針を確認してからスタートするようにしましょう。
公務員でも株式投資をしても問題ない?法的根拠から注意点まで徹底解説
不労所得にどんな種類があるのか知りたい人によくある質問
不労所得の種類を知りたい人によくある質問は、以下のとおりです。
- 不労所得で月50万円稼ぐ方法は?
- 不労所得には税金がかかる?
それぞれみていきましょう。
不労所得で月50万円稼ぐ方法は?
不労所得で月50万円を達成する現実的な方法として、不動産投資が挙げられます。
たとえば、利回り14%が期待できる7,500万円の一棟マンションをローンで買って運用すると月50万円の不労所得が手に入ります。
年間の総収入は1,050万円となりますが、ローン返済や管理・修繕費、税金などの諸経費を差し引くと実際の手取り月収は50万円程度です。
ただし、不動産投資を成功させるためには、綿密な計画や継続的な学習が必要となるため、初心者にはハードルが高い点に注意が必要です。
不労所得には税金がかかる?
不労所得であっても、一定額以上の収入があれば課税対象です。
たとえば、株式による配当所得や債券による利子所得には20.315%の税金がかかります。
また、不動産所得は総合課税として他の所得と合算し、累進税率(5%〜45%)により課税されます。
なお、累進税率とは、所得金額が増えるほど税率が上がる仕組みです。
気をつけておきたいのが、上記のように不労所得の種類によって税率や計算方法が異なるため、事前に税務の基礎知識を身につけておくのが重要です。
ちなみに、税理士に相談したり、税務署の無料相談を活用したりして、適切な税務処理を行うと余計な税負担を避けられます。
まとめ
今回は、不労所得の種類と特徴について解説しました。
不労所得には金融資産型・不動産収入型・デジタル型・権利型の4つの種類があり、それぞれ初期コストや収益化までの時間が大きく異なります。
不労所得を目指す際に重要なのは、「楽に稼げる」という甘い考えを捨て、準備段階での相当な努力が必要だと理解することです。
また、詐欺被害への注意や勤務先の就業規則の確認など、事前に把握しておくべき注意点もあります。
ぜひ本記事を参考に、自分に適した不労所得の手法を見つけて、計画的で長期的な視点での資産形成をはじめてみてください。
サラリーマンがセミリタイアを成功させる方法!実現するための具体的なステップ

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。