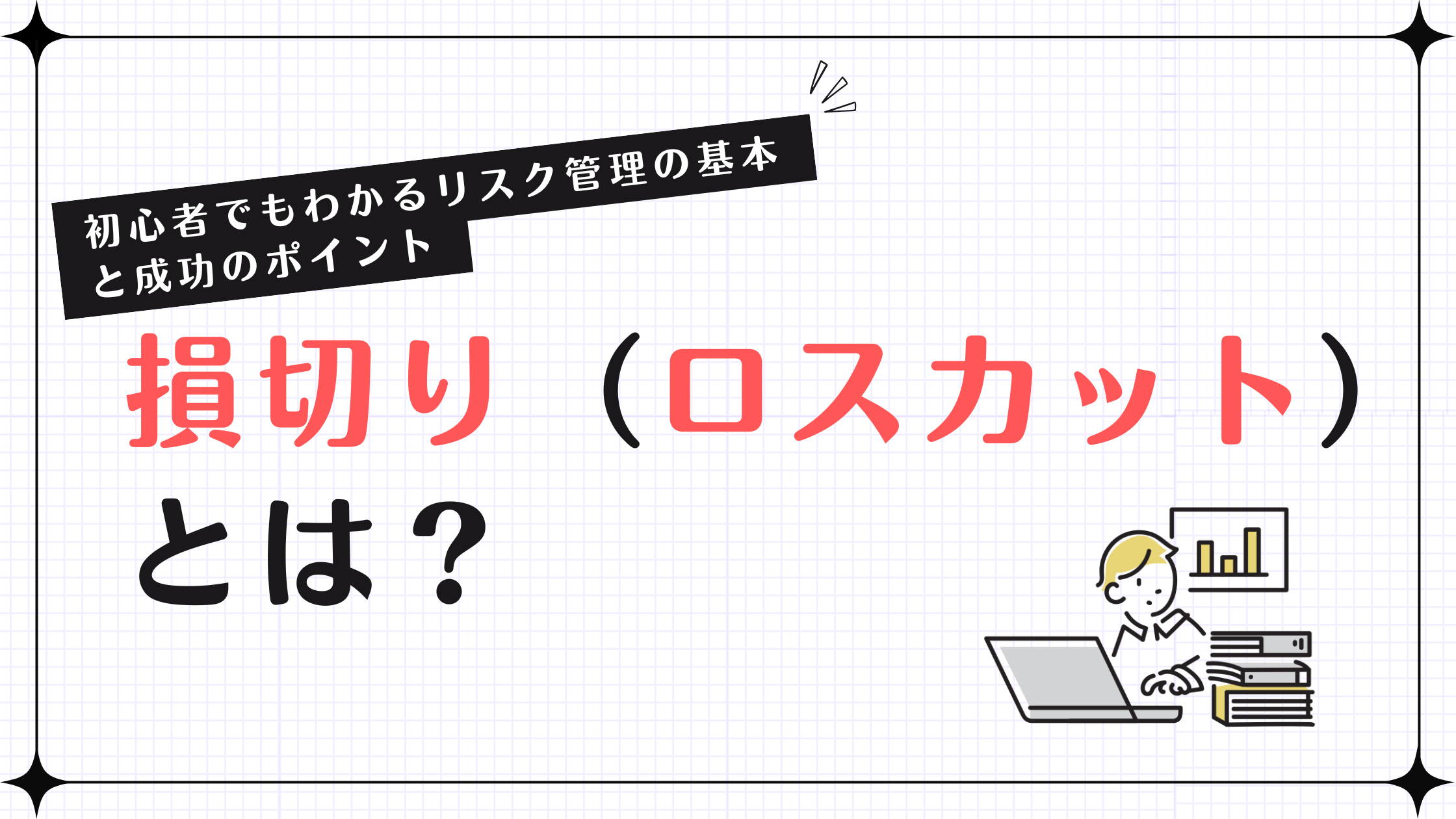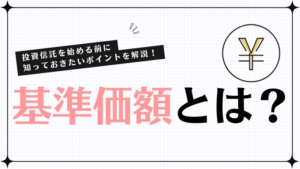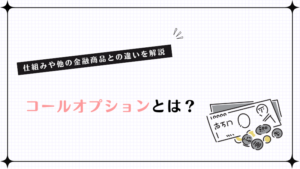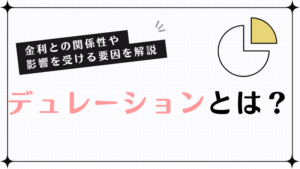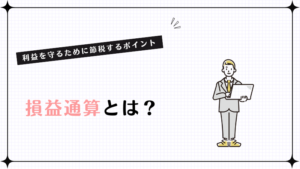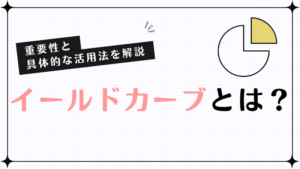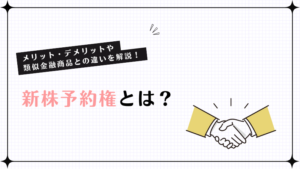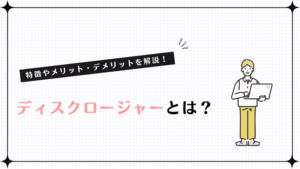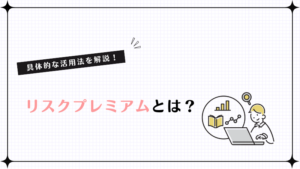株式投資で避けて通れない「ロスカット(損切り)」。
損失を限定するための行動ですが、「どこで」「どう決めるのか」が難しいポイントです。
本記事では、ロスカットの意味や損切りとの違い、実際の判断基準、心理的な壁の克服法までを体系的に整理。
初心者が感情に左右されず、リスクをコントロールできるようになるための基礎をわかりやすく解説します。
ロスカット(損切り)とは何か
株取引では、想定外の値動きによって損失を抱えることがあります。その損失を一定範囲で止めるために行うのが「ロスカット」です。
ロスカット(Loss Cut)とは、保有株の損失が一定額に達した際に売却し、損害を最小限に抑える行動を指します。
「損切り」との違いは厳密にはほとんどなく、一般的には「ロスカット=取引ルールとしての損切り」と理解されます。
ロスカットは“負けを認める”行為ではなく、“資産を守る”ためのリスク管理です。
ロスカットの重要性と生活の例え
ロスカットを避けると、損失は雪だるま式に膨らむリスクがあります。投資だけでなく、日常生活でも「早めの対処」が重要です。
歯医者に行くケース
例えば、歯医者に行く場合を想定してみます。
「ちょっと歯が痛むかな」という段階で歯医者に行けば、歯を丸々失うことなく初期治療で完治するケースが多いでしょう。
しかし、「ちょっと歯が痛いけど、そこまでではないから我慢しておこう」と考えてやり過ごしていると、歯を丸ごと失うリスクが大きくなってしまいます。
同様に株式投資のケースを見てみましょう。
株式投資のケース
自分が買い注文で保有している銘柄が、想定以上に株価下落をしています。
ここで、「少し損失が出てしまったが、被害が少ないうちにいったん手仕舞いして思考をリセットし、あらためてチャート分析をしてから売り注文の判断をしよう」という考え方が損切りの考えです。
それとは逆に、「まだ復活する可能性があるから、信じてそのまま様子見しよう」という考え方もあります。
これは、よほどの根拠がない限りは、想定した通りに株価が動くことは少ないので、危険な考え方であるといえるでしょう。
ロスカットのメリットとデメリット
ロスカットはリスク管理の基本ですが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。
ここでは主な利点と注意点を整理します。
損切りのメリット
損切りのメリットとして考えられるのは、損失の金額を最小限に喰い止めることができる点です。
人間の心理として、損失が出てしまうと自分のトレードに対するネガティブイメージが強くなってしまい、正常な決断ができなくなるケースが多いのですが、上手く損切りができるようになっておくと、たとえ損失が出ている状況でも平常心で対処できるようになるでしょう。
早い段階で損切りをすることで、メンタルを一旦リセットすることができるので、その後のトレードで引きずることが少なくなります。
もちろん、損失を出してしまったという多少のネガティブな感情は発生しますが、損失が拡大してしまってからと比べれば格段に立ち直るのが楽でしょう。
損切りのデメリット
損切りのデメリットとして考えられるのは、必要のない場面での損切りをしてしまい、利益を逃してしまうことです。
俗に言う「損切り貧乏」というものですね。
例えば、上昇トレンドに向かう手前で、一時的に株価が下がったとしましょう。
そのタイミングで損切りをしてしまうと、いざ上昇トレンドに再突入した場合に利益を取りこぼしてしまうことがあります。
そうしたデメリットを防ぐためには、損切りに対する正しい知識を身に付け「リスクヘッジ」を意識したトレードをすることで、対応ができるようになります。
リスクヘッジに関する詳細は後述します。
損切り貧乏を防ぐには?
根拠のない感覚的な損切りは、損切り貧乏の原因になります。
防ぐためには、チャート上の根拠(支持線・抵抗線・移動平均線など)や、リスク許容率(総資金の2〜3%など)を明確にしておくことが重要です。
エントリー前に「損切りライン」と「利確ライン」をセットで設定しておくことで、感情ではなくルールで判断できるようになります。
損切りできない心理とプロスペクト理論

損切りができない人は、行動経済学の中で知られている「プロスペクト理論」の回避心理が働いていると考えられます。
これは、例えば下記のようなケースを考えてみてください。
- :無条件で必ず1万円を支払わなければならない
- :コインを投げて表がでたら支払いは免除される。ただし、裏が出たら3万円を支払わなければならない
この場合は、ほとんどの人が2.の行動を選んでしまうようです。
つまりは、人間は確実に損失が出るケースを避けようとして、失敗すればより大きな損失が出てしまう方を選んでしまいがちということが言えます。
「1万円を払いたくない」という焦りから、この「失敗すれば」の五分五分の恐ろしさに気づくことができず、正しい判断能力を失ってしまうのです。
これは、株式投資でも同じことが言えます。
「損失を回避したい」という思いは、誰もが持っています。
ここで自制心を持って損切りの判断ができる人が、トレードの世界で生き残れる人なのです。
リスクを抑えるロスカットの考え方
ロスカットは単なる「損を止める」行為ではなく、リスクを設計する仕組みです。次の3ステップで整理してみましょう。
損切りラインの決め方
損切りラインは「許容損失」と「チャートの形」から導き出します。
たとえば、購入価格から−5%や、直近安値を下回った地点など、具体的な数値や価格帯を基準に設定する方法があります。
一貫性を持たせることで、感情ではなくデータで判断できるようになります。
ロスカット注文の活用法
証券会社のシステムでは、あらかじめ損切り価格を指定して自動で注文する「ロスカット注文」や「逆指値注文」が利用できます。
これを使えば、相場が急変しても感情的な判断を避け、事前に定めたルールで損失を限定できます。
両建て・建玉操作によるヘッジ
上級者向けの方法として「両建て」があります。
買いポジションを保有したまま、売りポジションを追加して値動きリスクを相殺する手法です。
相場が反転した際に損益のバランスを保ちやすく、心理的負担も軽減されます。
損切りに関するよくある質問(Q&A)
Q1. 損切りラインはどうやって決めればよいですか?
A. 損切りラインは「自分の許容できる損失額」や「チャート上の重要な価格帯(支持線・抵抗線)」を基準に設定するのが一般的です。
初心者は、エントリー時に必ず損切り価格を決めてから取引を始める習慣を持つと、感情に左右されずに実行しやすくなります。
Q2. 損切りばかりで利益が出ない場合、どう対処すればよいですか?
A. 損切りが多すぎるのは、エントリーの根拠が弱い可能性があります。
トレンドの方向性を確認してから取引する、出来高や移動平均線など複数の指標を組み合わせることで精度を高めましょう。
また「損切りは必要経費」と考え、1回の損失よりもトータルで利益を残せるかどうかを意識することが大切です。
まとめ
ロスカットとは、損失を限定し資産を守るための基本ルールです。
早めの判断が損失拡大を防ぎ、冷静な取引を続ける力になります。
心理的な恐怖を克服し、感情ではなくルールで行動することで、安定したトレードを長期的に続けることが可能になります。
ロスカットは「負けを認めること」ではなく、「次に勝つための準備」であるという視点を持ちましょう。
株の勉強は絶対にやるべき!オススメ勉強ステップや失敗しないためのコツ

著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。
地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。
その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。