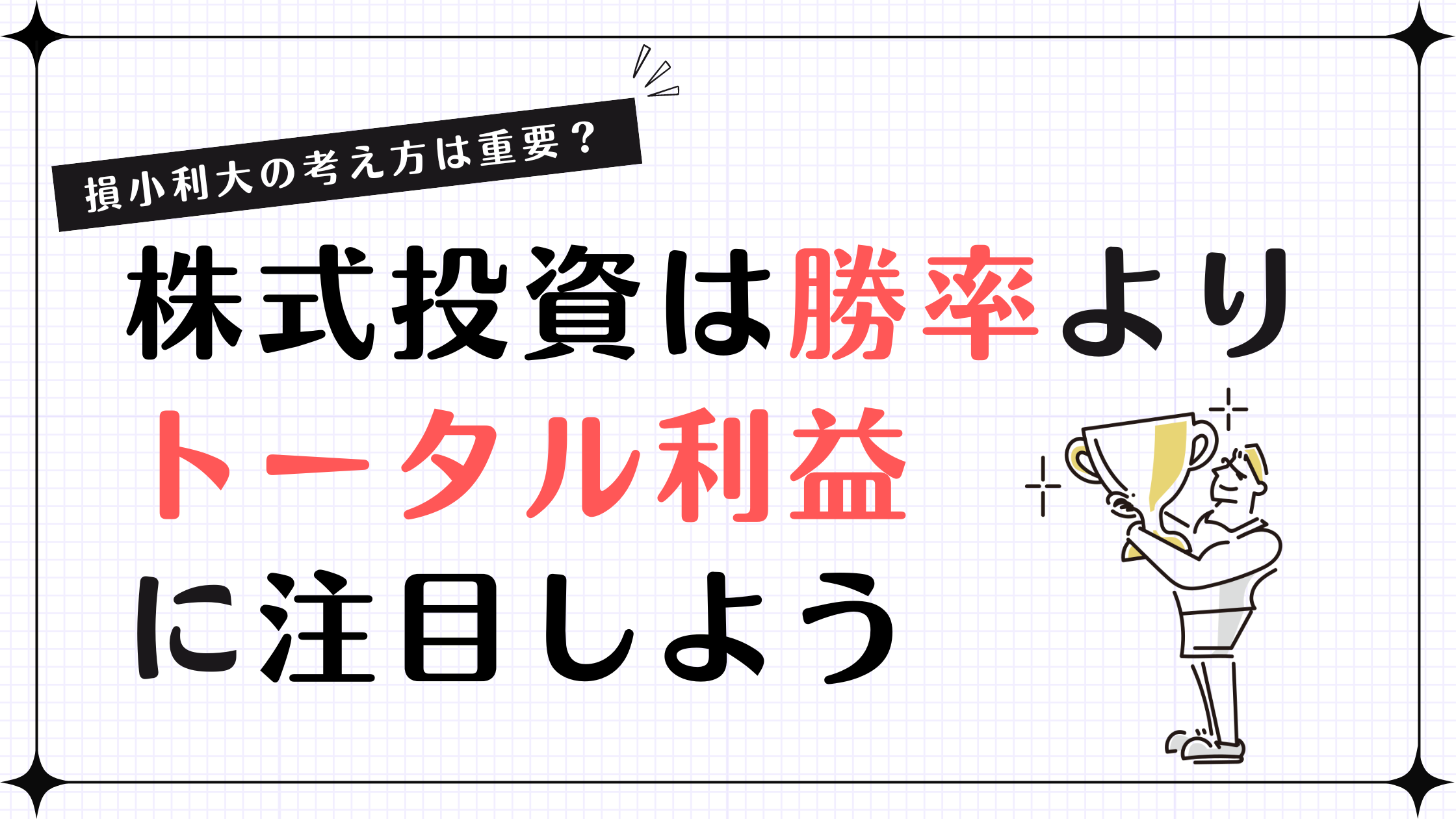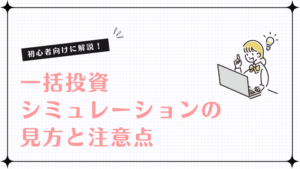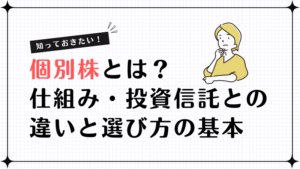株式投資の世界では、「損小利大(そんしょうりだい)」という言葉がしばしば登場します。
直訳すると「損は小さく、利益は大きく」という意味ですが、その本質は“勝率よりもトータルで勝つ”という考え方にあります。
初心者ほど「勝ち負けの回数」に注目しがちですが、実際に投資で成果を出す人は、勝つ回数ではなく、勝った時の利益の大きさを重視しています。
本記事では、損小利大の意味や重要性、そして実践のために必要な考え方やトレード技術を詳しく解説します。
損小利大の考え方が重要な理由
まず株式投資において、損小利大の考え方はどのように重要なのか考えてみましょう。
短期での株式投資を頻繁に行っていると「勝率」に目が行きがちです。
例えば下記のような取引を行った場合、勝率は2勝1敗となります。
- 1回目の取引:1,000円の利益
- 2回目の取引:5,000円の損失
- 3回目の取引:3,000円の利益
しかしトータルの利益は4,000円の利益に対して5,000円の損失となり、差し引き1,000円のマイナスとなってしまうのです。
勝率が良くてもトータルで損をしてしまっては元も子もありません。
では「損小利大」の考え方にそって下記のような取引を行った場合はどうでしょうか。
- 1回目の取引:1,000円の損失
- 2回目の取引:2,000円の損失
- 3回目の取引:10,000円の利益
勝率は1勝2敗でマイナスですが、トータルの利益は3,000円の損失に対して10,000円の利益となり差し引き7,000円のプラスになります。
株取引においては、勝率を上げるよりもトータルで利益を出すことの方が大切であることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。
トータルで利益を出すために重要になるのが、損小利大の考え方なのです。
損小利大を実践するための3つのポイント
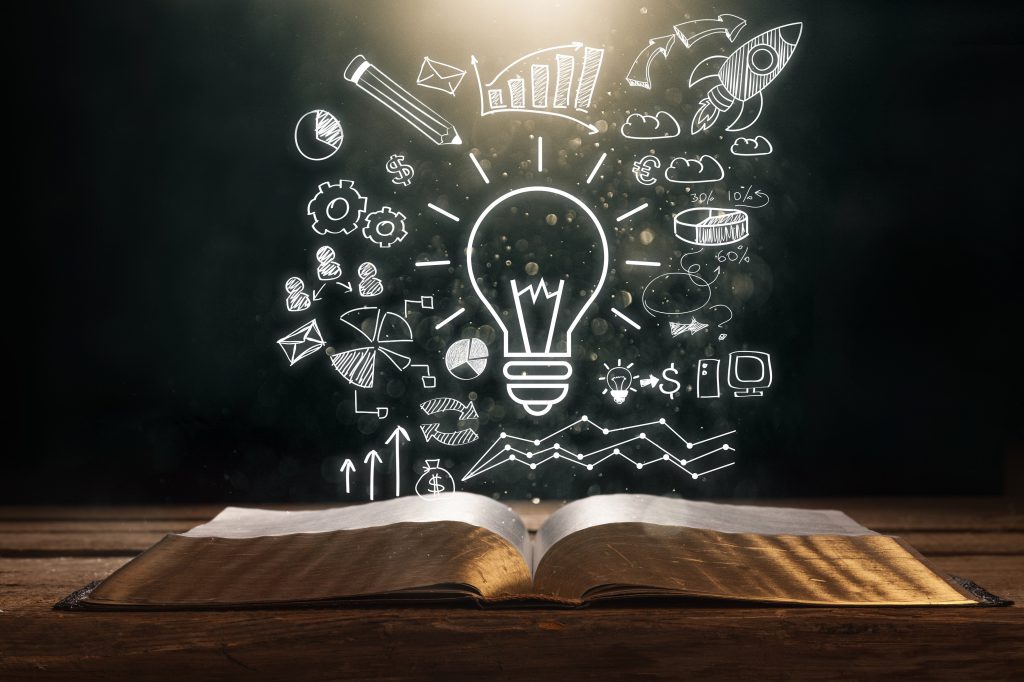
損小利大は頭で理解しても、実際のトレードで実践するのは簡単ではありません。
特に「損切りが遅れる」「早く利確してしまう」といった心理的な壁が大きな課題です。
ここでは、実践するための3つの具体的ポイントを紹介します。
① 損切りラインを“事前に”決めておく
「株価が下がったらどうしよう…」という不安をなくすには、エントリー時点で損切りラインを決めておくことが大切です。
たとえば「購入価格から5%下落したら売る」など、明確な基準を設けておきましょう。
このルールを守るだけで、「気づいたら大損していた」という事態を防げます。
損小利大の“損小”部分は、習慣づけとルールの徹底がカギです。
② 利益確定の目標を“広めに”設定する
初心者に多いのが、「少し利益が出たから早めに売ろう」という行動です。
しかし、利益を伸ばすには“もう一歩粘る”勇気が必要です。
目標を「5%の利益が出たら売る」から「10%上昇で売る」に変えるだけでも、トータルのリターンは大きく変わります。
もちろん、欲張りすぎて売り損ねないよう、チャートのトレンドや出来高を確認しながら判断しましょう。
③ 損益比率(リスクリワード)を意識する
損小利大の本質は、「1回の利益で数回の損をカバーできる構造を作る」ことです。
そのために意識したいのがリスクリワード比(利益:損失)です。
たとえば「利益目標10%・損切り5%」で取引すれば、リスクリワード比は2:1です。
このバランスを保てば、勝率が50%以下でもトータルでプラスになります。
損小利大を妨げる心理のワナ
多くの投資家が“損小利大”を理解していても、実際には「損大利小」になりがちです。
その原因は、人間の心理にあります。
① 損失回避バイアス
人は「損を確定させたくない」という心理が強く働くため、下落しても損切りできずに保有し続けがちです。
結果、損失が膨らみやすくなります。
② 利益確定欲求
一方で、少しでも利益が出ると「今のうちに確定したい」という欲求が出ます。
この“早すぎる利確”が、損小利大を崩す大きな要因です。
③ 群集心理への同調
SNSやメディアで話題になる銘柄を“安心材料”として買うケースもありますが、多くの場合はトレンドの終盤。
他人の判断に左右されると、冷静なトレードが難しくなります。
損小利大を実現するためのトレードの技術とは
感情に左右されず、再現性のある判断をするためにはテクニカル分析とルール化が欠かせません。
-
移動平均線(トレンドの方向を確認)
-
MACD(勢いの強弱を測る)
-
RSI(買われすぎ・売られすぎを判断)
これらを組み合わせ、チャートの「波」を分析することで、感情ではなくデータに基づいたトレードが可能になります。
当サイトの監修者・相場師朗先生のような熟練トレーダーは、こうしたテクニカルを“再現可能な型”として体系化し、感情を排した売買ルールを確立しています。
つまり、損小利大を実践するには、「感情」ではなく「技術」で判断する力」を鍛えることが重要なのです。
【相場式株技術用語】下半身・逆下半身とは?株初心者にもわかりやすく解説します
よくある質問(Q&A)
Q1. 損小利大を意識しても、なかなか実践できません。どうすれば良いですか?
A. 最初は紙に「損切りライン」と「利益目標」を書いてから取引するのがおすすめです。
数値化して“見える化”することで、感情よりルールを優先しやすくなります。
Q2. 損小利大を身につけるのにどれくらい時間がかかりますか?
A. 個人差がありますが、数週間〜数カ月は必要です。
まずは少額で取引を繰り返し、自分の心理のクセを客観的に分析することから始めましょう。
Q3. 損切りが怖くて行動できません。どうすればいいですか?
A. 「損切り=負け」ではなく、「損切り=次のチャンスに資金を残す行為」と考えましょう。
1回の負けで撤退せずに続けられる人こそ、結果的に勝ち残ります。
まとめ
損小利大の考え方は、投資の世界で最も重要な原則の一つです。
勝率が高くても損失が大きければ資金は減り、逆に勝率が低くても利益を大きく伸ばせればトータルでは勝てます。
損小利大を実践するには、
-
エントリー前に損切りと利確の基準を決める
-
感情ではなくデータとルールで判断する
-
再現性のあるトレード技術を身につける
という3つのステップを徹底することが重要です。
「負けを小さく、勝ちを大きく」──このシンプルな原則を日々のトレードに落とし込むことが、長期的に利益を積み上げる近道です。
焦らず、ルールを守り続けることで、損小利大の真価は必ず実感できるでしょう。
株の勉強は絶対にやるべき!オススメ勉強ステップや失敗しないためのコツ

著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。
地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。
その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。