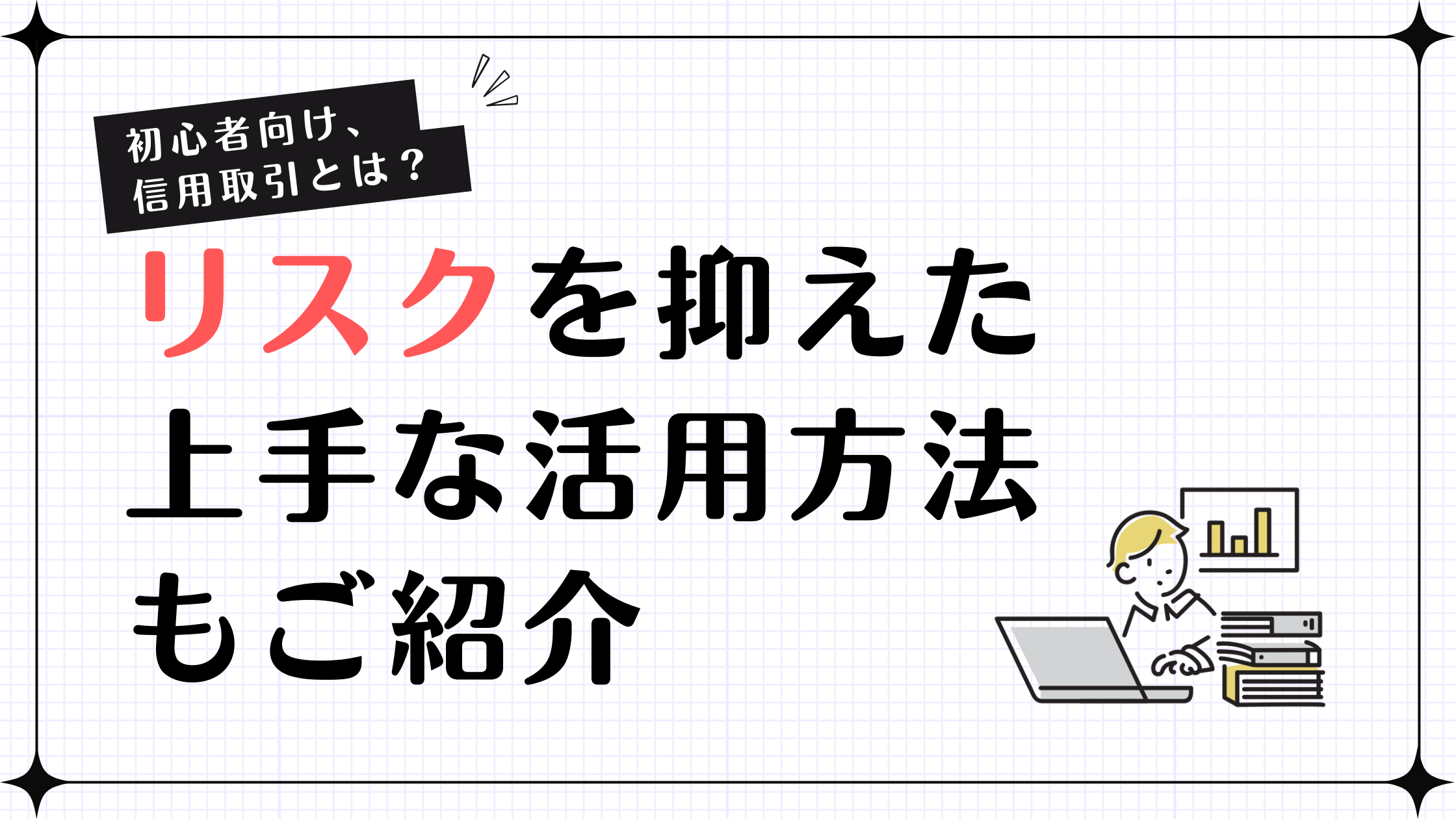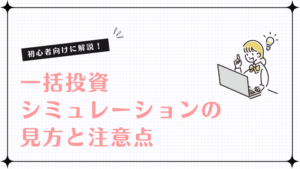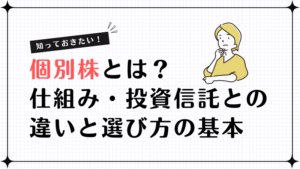信用取引は「元手以上の取引ができる」「空売りが使える」と聞く一方で、追証や強制決済などの言葉から不安を感じる方も多いと思います。
本記事では、現物取引との違いから、証拠金や委託保証金維持率、制度信用と一般信用の特徴、レバレッジや空売りのメリットとリスクまでを整理して解説します。
仕組みとリスク構造を理解し、自分にとってどのような選択肢かを考えるための基礎知識として活用してください。
信用取引とは
信用取引は、自己資金を担保として証券会社から資金や株式を借り、元手以上の取引を行える仕組みです。
現物取引と比べてできることが増える一方で、損益の振れ幅も大きくなります。
まずは、現物取引との違いや、信用取引でどのような取引が可能になるのかといった基本から整理してみましょう。
現物取引との違い(資金・決済方法・リスク構造)
信用取引を理解する際は、現物取引との違いを押さえると全体像がつかみやすくなります。
現物取引では、自分が用意した資金の範囲内で株式を購入し、その株式を保有する形になります。
価格が下落しても保有し続けるか売却するかは原則として投資家が判断し、強制的に決済される仕組みは基本的にありません。
一方、信用取引では、自己資金を委託保証金として証券会社に預け、その保証金を担保にして資金や株式を借りて取引を行います。
元手に対して数倍の取引が可能になるため、同じ値動きでも損益の金額は大きくなります。
また、返済期限が定められていることや、委託保証金維持率が一定水準を下回ると、追証や強制決済が発生する仕組みも特徴です。
このように、資金の使い方や決済ルール、リスクの出方が現物取引と異なることを理解しておくと、信用取引がどのような位置づけの取引なのかをイメージしやすくなります。
信用取引でできること(買建と売建)
信用取引では、担保を差し入れることで「買建」と「売建」という二つの形でポジションを持つことができます。
買建は、証券会社から資金を借りて株式を購入する取引で、値上がりによる差益を目指すという点では現物取引と似た動きになります。
ただし、借りた資金を用いているため、決済期限や金利負担などが生じます。
売建は、証券会社から株式を借りて売却し、その後買い戻して返却する取引です。
株価の下落局面でも、売建を通じて値下がり幅に応じた損益が発生するため、相場が下がっている場面でもポジションを持てる選択肢が広がります。
例えば、1株100円の株式を借りて売却し、80円で買い戻せば、その差額20円が損益の対象になります。
このように、信用取引では上昇局面だけでなく下落局面も取引の対象に含めることができますが、その分ルールやリスクを把握しておくことが大切です。
信用取引の仕組み

信用取引の仕組みは、証券会社から資金や株式を借りて株式投資を行う、証拠金取引で成り立っています。
証拠金とは
証拠金とは、元本と同じ意味で証券会社に預け入れる資金を指します。証券会社は投資家から預けられた資金を担保に、同額か数倍以上の資金や株式を貸します。
数倍以上の取引を行うことをレバレッジ取引と呼びます。信用取引の仕組みを利用すると、少額資金を元手に大きな取引を行うことが可能です。
また、通常は買い注文からのトレードしかできませんが、信用取引の仕組みを活用することで、売り注文からトレードをスタートさせることも可能です。
審査や委託保証金について
信用取引を始めるためには、審査の通過と定められた金額以上の元本を預け入れなければ、取引を始めることができないようになっています。審査は主に収入や職業など基本情報から判断されます。
さらに、委託保証金(元本・担保金)は、法律で取引金額の30%以上預け入れる必要があると定められています。
委託保証金維持率(証拠金維持率)について
委託保証金維持率とは、取引した金額に対する元本の割合のことです。
取引を行って損失が発生した際、委託保証金維持率が一定の割合を下回ると強制決済となり、追証する必要が出てきます。追証(追加保証金)とは、不足している保証金へ新たに資金を追加することです。
信用取引の仕組みを理解する上で、委託保証金維持率は特に重要なポイントになります。実際に利用する際は、委託保証金維持率のチェックを忘れないようにしましょう。
信用取引の種類

信用取引の種類には、制度信用取引と一般信用取引が存在します。大きな違いは、契約相手や取引できる銘柄、返済期限です。
制度信用取引とは
制度信用取引は、証券取引所が制度信用銘柄選定基準を満たした、と判断できる銘柄のみと取引ができます。制度信用銘柄選定基準は、東京証券取引所の規則に定められていますが、今回は省略します。
1回の取引に掛かる資金は、返済期限6カ月以内と一律で決められています。また、銘柄選定の審査が厳しい分、金利は低めに設定されている点も特徴的です。
一般信用取引とは
一般信用取引も、取引自体は制度信用取引と同様ですが、証券取引所ではなく証券会社が取り決めた金利や返済期限等のルールに則って行います。
制度信用取引と違い、証券会社ごとに金利設定や返済期限が異なります。また、銘柄選定についても証券会社のルールに基づいて選定されており、各証券会社で違いがあります。
信用取引のメリットは空売りができること
信用取引のメリットは、元本以上の取引や空売りができることです。
自身が用意した資金でトレードするのではなく、証券会社から借りた資金や株式でトレードができるため、売り注文からトレードを始めることができます。いわゆる「空売り」のことで、株式を売って保有銘柄を買い戻すトレードです。
トレードの流れと利益を得る例を以下にご紹介します。
- 1株100円のA株式を、1株式だけ証券会社から借りる。
- 1株式を現在価格100円で売り注文に出す。取引成立。
- 100円を得る。1株80円まで下がったところで買い注文を出す。
- 1株80円で取引成立。100円のうち80円を使って1株を買い戻す。
- 借りていた1株を証券会社へ返済し、残った20円を利益として得る。
このように下落のトレンドで利益を得られる点が、信用取引のメリットでもあります。
当サイトを監修していただいている、「相場師朗(あいばしろう)先生」は、この「空売り」で多くの利益を上げていらっしゃいます。
現物取引のみであれば、利益を取れる幅も限られてきますが、空売りでも利益を狙えるようになれば、トレードの幅が大きく広がることでしょう。
また、元本の2~3倍の資金や株式を借りた取引、いわゆるレバレッジ取引が可能になるため、より大きな利益を求めたい場合に活用できます。
信用取引のリスクは資金管理と期限
信用取引には、空売りやレバレッジといった特徴に加え、返済期限や金利・貸株料、追証・強制決済など、現物取引とは異なるリスクがあります。
ここでは、レバレッジによる損失拡大や期限・コストに関するリスクを整理し、信用取引のリスク構造を俯瞰して確認していきます。
レバレッジによる損失拡大リスク
レバレッジ取引では、自己資金に対して数倍のポジションを持つことができるため、価格が想定と逆方向に動いた場合には、損失が自己資金を大きく上回る速度で拡大する可能性があります。
特に、価格変動が大きい銘柄や相場環境では、短期間の値動きで委託保証金維持率が急速に低下することがあります。
委託保証金維持率が基準を下回ると、追証の入金やポジションの縮小が必要になり、相場状況にかかわらず決済を迫られることもあります。
また、レバレッジを高く設定している場合、少しの値動きでも維持率が変化しやすく、結果的に取引の自由度が狭まる場合もあります。
このような構造から、レバレッジの設定は、取引機会を広げる一方で、損失が拡大しやすい方向にも作用することになります。
信用取引を理解するうえでは、レバレッジによって損益の振れ幅がどの程度変化するのかを意識しておくことが重要です。
返済期限・金利・貸株料などコスト面のリスク
信用取引には、返済期限がある点や、金利・貸株料といったコストがかかる点もリスク要因になります。
制度信用取引では返済期限が6か月以内などと決められており、その期間内に反対売買や現引き・現渡しなどで建玉を解消する必要があります。
期限までに想定していた値動きにならない場合でも、決済を検討しなければならない場面が出てきます。
また、買建では建玉に対して金利が、売建では貸株料や逆日歩などのコストが発生することがあります。
これらのコストは、保有期間が長くなるほど累積し、最終的な損益に影響します。
配当や株主優待の権利付き最終日付近では、売建ポジションに特有のコストが変動するケースもあるため、取引条件を確認しておくことが大切です。
返済期限やコストの存在により、信用取引では「時間」と「費用」の両面で現物取引とは異なる制約が生じます。
取引を検討する際には、値動きだけでなく、これらの要素も合わせて考える必要があります。
信用取引のリスクを抑えた上での活用法
信用取引は、リスク構造を理解したうえで利用されることが多い取引手法です。
ここでは、「こうした場面で用いられることがある」という代表的な活用パターンと、ポジションサイズやレバレッジを考える際の視点を紹介します。
具体的な取引を推奨するものではなく、仕組みを理解するための参考例としてご覧ください。
ヘッジやつなぎ売りなど代表的な活用パターン
信用取引は、単に値上がりや値下がりを狙う手法としてだけでなく、保有している株式の価格変動リスクを抑える「ヘッジ」目的で利用されることもあります。
例えば、現物で一定の銘柄を保有している場合に、短期的な下落リスクを意識し、同じ銘柄や関連銘柄を信用取引の売建で持つことで、ポートフォリオ全体の値動きを緩和する考え方があります。
また、配当や株主優待を受け取りつつ、価格変動リスクを抑えるための手法として「つなぎ売り」と呼ばれる活用例が紹介されることもあります。
これは、現物と信用取引を組み合わせて、特定の期間の値動きに対する影響を調整する考え方です。
いずれの場合も、仕組みが複雑になるほど、必要な知識や確認すべき条件が増えます。
ヘッジやつなぎ売りといった手法に触れる際は、メリットだけでなく、コストやリスク、条件を一つずつ整理して理解することが重要です。
ポジションサイズとレバレッジの考え方
信用取引を利用する際には、「どのくらいの規模のポジションを持つか」というポジションサイズの考え方が重要になります。
自己資金の範囲内でどの程度まで評価損を許容できるか、どの水準で維持率が変化するかといった点を把握し、取引金額を調整することが、リスク管理につながります。
レバレッジについても、最大限に活用するのではなく、自己資金に対してどの倍率までなら値動きに対応できるかという視点で考えられることが多いです。
例えば、法令上や証券会社の上限が3倍であっても、実際には1〜2倍程度に抑えるなど、自分なりの目安を持つ考え方があります。
ポジションサイズとレバレッジは、取引の自由度とリスクのバランスを左右する要素です。
信用取引を学ぶ際には、個別銘柄の選択と同じくらい、これらの設定がどのようにリスクに影響するかを意識しておくと、全体像をつかみやすくなります。
【よくある質問】信用取引を始める前に知っておきたいこと
Q1. 信用取引は初心者でも始められますか?
A. 始めることは可能ですが、審査や最低保証金の入金が必要です。
また、現物取引と異なり「レバレッジ」や「空売り」が使える分、損失が膨らむリスクも伴います。
そのため、まずは現物取引で基礎を身につけてから、少額で信用取引を試すのが安全です。
Q2. 信用取引で大きな損失を避けるにはどうすれば良いですか?
A. 最も重要なのは「資金管理」です。
レバレッジをかけすぎず、委託保証金維持率を常にチェックすることが欠かせません。
また、下降トレンドでの空売りや建玉操作を活用することでリスクヘッジも可能です。
加えて、返済期限がある点を意識し、長期保有を前提にしない戦略を立てましょう。
まとめ
信用取引は、委託保証金を担保として元手以上の取引を行い、買建と売建を使い分けられる取引手法です。
現物取引にはない空売りやレバレッジを通じて、上昇・下落の両方の局面でポジションを持つ選択肢が広がる一方で、返済期限や金利・貸株料、委託保証金維持率、追証・強制決済など、特有のリスク構造も備えています。
制度信用と一般信用の違い、レバレッジによる損益の変化、コストや期限の影響を理解しておくことで、信用取引を「現物とは異なる仕組みを持った一つの選択肢」として捉えやすくなります。
実際に利用するかどうかを検討する際には、まず仕組みとリスクを整理し、自分の資金や経験、リスク許容度に照らして判断することが大切です。

著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。
地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。
その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。