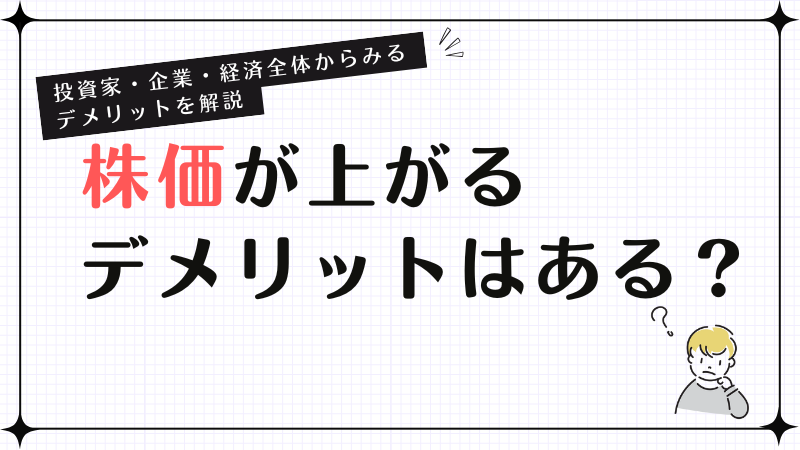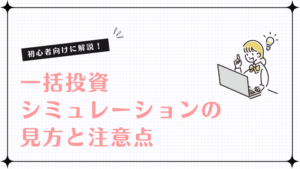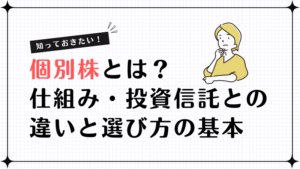「株価が上がるデメリットはあるの?」と疑問に思っていませんか?
多くの方にとって、株価上昇は利益につながる理想的な状況に思えるかもしれませんが、実はいくつかのリスクも存在します。
そこで今回は、株価上昇が投資家・企業・社会経済に与えるデメリットについて詳しく解説します。
本記事を読むと、投資初心者の方でも株価上昇の裏側にあるリスクや注意点を理解することが可能です。
ぜひ本記事の内容を参考に、株価上昇によるデメリットについて理解を深めてください。
株価が上がることによるデメリットはある?
基本的に株価上昇は、様々な好影響をもたらす場合が多いです。
たとえば、投資家にとっては投資リターンの向上といった恩恵を受けられます。
また、経済や社会全体にとっても雇用創出や消費拡大など、様々なメリットを享受することが可能です。
上記のように「株価が上がるのは良いことばかり」だと考えがちですが、その裏にはデメリットとなるリスクも存在します。
次の章からは、株価が上がることによるデメリットを投資家・企業・経済の面から詳しく解説していきます。
株価の決まり方がわかる!株価変動のメカニズムと実際の影響を徹底解説
株価が上がると投資家にとってどんなデメリットがある?
投資家にとって、株価が上がることによるデメリットは以下のとおりです。
- 買い時を逃す可能性がある
- 高値掴みリスク
- 配当金利回りが下がる
それぞれみていきましょう。
買い時を逃す可能性がある
株価が上昇している局面では、不安や恐怖から買う決断ができず、結果的に最適な買い時を逃してしまう可能性があります。
人間の心理として、価格が上がっている商品に対してはリスクを感じやすくなり、判断が遅れがちになるからです。
たとえば、株価が急騰している銘柄をみて「今買っても遅すぎる」と感じて手を出せずにいたところ、その後も上昇が続いて大きな機会損失になるケースがよくあります。
株価上昇時は心理的要因により、本来であれば利益を得られるはずの投資機会を逃してしまいやすくなるのがデメリットの一つだといえます。
高値掴みリスク
株価上昇時に投資初心者が警戒すべきなのが、高値掴みのリスクです。
株価が上がっている時期は「まだ上がるはず」という期待が先行しやすく、実際の企業価値を超えた割高な価格になる場合があるからです。
もし実際の企業価値以上のときに株を購入したら、株価が実態に戻る際に大幅な下落による損失を被る可能性があります。
株価の上昇は利益を得る機会となりますが、同時に高値掴みリスクがあることを理解し、投資判断の際には十分な注意が必要です。
配当金利回りが下がる
株価上昇による配当金利回りの低下が、デメリットの一つとして挙げられます。
配当利回りは「年間配当額÷株価」で計算されるため、企業が支払う配当金額が変わらなくても、株価が上昇すると自動的に利回りが下がるからです。
たとえば、年間配当が1株当たり50円の企業があったとして、株価が1,000円から2,000円に上昇した場合、配当利回りは5%から2.5%へと半減します。
同じ資金を投じても実質的に受け取れる利回りが減少するため、配当収入を重視する投資家にとっては、買い増しする際はデメリットとなる場合があります。
配当金目当ての投資を考えている投資家の方は、株価の動きと配当利回りの関係を確認し、期待する利益や投資方針と合致しているかを検討するのが重要です。
株価が暴落するとどうなる?その後の投資戦略と回復に向けた対策を徹底解説
株価が上がると企業にとってどんなデメリットがある?
企業にとって、株価が上がることによるデメリットは以下のとおりです。
- 経営にプレッシャーがかかる
- 株価上昇が続くと市場から期待値が異常に高くなる
それぞれみていきましょう。
経営にプレッシャーがかかる
株価が上昇すると、株式価格の維持やさらなる上昇が期待されます。
このプレッシャーが、企業にとってデメリットになる可能性もあります。
なぜなら、株主からのプレッシャーにより、長期的な企業成長よりも短期的な利益を重視した意思決定を行う場合があるからです。
たとえば、将来の競争力向上に必要な設備投資や新技術への投資を先送りして、短期的なキャッシュフローを改善しようとすることがあります。
すると、長期的な競争力や成長力が低下し、結果的に企業価値の持続的な向上が困難になってしまいます。
上記のように、株価上昇が企業の成長を阻害する要因となる可能性が、少なからずあることを理解しておきましょう。
株価上昇が続くと市場から期待値が異常に高くなる
継続的な株価上昇は、市場参加者の期待値を現実的な水準を超えて押し上げてしまう危険性があります。
投資家や市場関係者が企業の将来性を過度に楽観視し、実現困難な成長率や業績目標への期待を抱くようになるからです。
過度な期待を背負った企業が予想される成長率や業績目標を達成できなかった場合、株価の急落や大量の失望売りを招きやすくなります。
市場の信頼を失墜させると、株価の大幅下落だけでなく企業の資金調達能力の低下により、事業展開への深刻な悪影響が生じる可能性があります。
株の勉強はなぜ必要?初心者におすすめのステップと失敗しないためのコツ
株価が上がると社会や経済にどんなデメリットがある?
社会や経済にとって、株価が上がることによるデメリットは以下のとおりです。
- バブルが起こりやすくなる
- 経済格差が広がる
- 生活コスト増加の可能性がある
それぞれみていきましょう。
バブルが起こりやすくなる
株価の持続的な上昇は、投資家心理の過熱による投機的な売買が増加するため、バブル経済を招きやすくなります。
バブルが崩壊した際の社会的・経済的な損失は計り知れません。
1980年代後半の日本のバブル経済では、不動産や株式の価格が実態から大きく乖離し、バブル崩壊時には多数の金融機関が破綻し長期的な経済停滞を招きました。
そのため、投資初心者はバブルの兆候を見極める目を養う努力を行い、市場全体が過熱状態にないかを常に意識するのが重要です。
経済格差が広がる
株価上昇は、経済格差の拡大を促進する側面があります。
現在の経済環境では、株式や不動産など資産運用による収益が、経済成長率を上回るケースが多く、既存の資産家がさらに富を蓄積しやすい構造になっているからです。
また、相続制度を通じて親から子へ富が受け継がれるため、努力や労働だけでは格差が埋まりにくいです。
働いて得られる収入よりも資産運用による収入の方が大きくなる現象は、格差拡大による社会不安を生む可能性があることも理解しておきましょう。
生活コスト増加の可能性がある
株価上昇は、一般消費者の生活コスト増加につながる可能性があります。
もし円安が影響して輸出企業が業績が良くなり、株価上昇が起こったのであれば、輸入品価格の上昇により食料品の値段やエネルギーコストが増加するからです。
また、株高によって金利上昇が起こると、住宅ローンや各種借入れの返済負担が重くなります。
このように、株価上昇と円安や金利上昇が組み合わさると、一般家庭の財布を圧迫する要因となる場合があります。
投資初心者はなにからはじめたらいいの?初心者におすすめの投資方法について解説!
株価が上がることによるデメリットを知りたい人によくある質問
株価が上がることによるデメリットを知りたい人によくある質問は、以下のとおりです。
- 株価が上がると為替はどうなる?
- 株価が上がると会社は儲かる?
それぞれみていきましょう。
株価が上がると為替はどうなる?
株価が上昇すると一般的に為替は、自国通貨高(日本の場合は円高)になる傾向があります。
なぜなら株式市場の上昇は、国の経済や企業業績が好調と評価されている証拠であり、より良い利回りを求めた海外投資家からの資金が流入するからです。
ただし為替相場は金利政策や景気動向、政治的要因など複数の要素が複合的に作用するため、株高が必ずしも通貨高につながるとは限りません。
市場環境によっては、株価と為替の関係が逆転するケースもあります。
株価が上がると会社は儲かる?
株価が上昇しても会社の売上や利益がすぐに増えるわけではありませんが、企業は間接的にメリットを得られます。
たとえば、株価上昇により企業の市場評価や社会的信用が向上し、金融機関からの資金調達が格段にしやすくなります。
また企業ブランドの向上により優秀な人材も集まりやすくなるため、経営基盤の強化を図ることが可能です。
上記のように、株価上昇自体が直接的な利益をもたらすわけではありませんが、資金調達力の向上や社会的信用の獲得など間接的な形で企業の経営安定に大きく寄与します。
【初心者必見】資産運用の基本を学ぶ!正しい勉強方法とステップ解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。