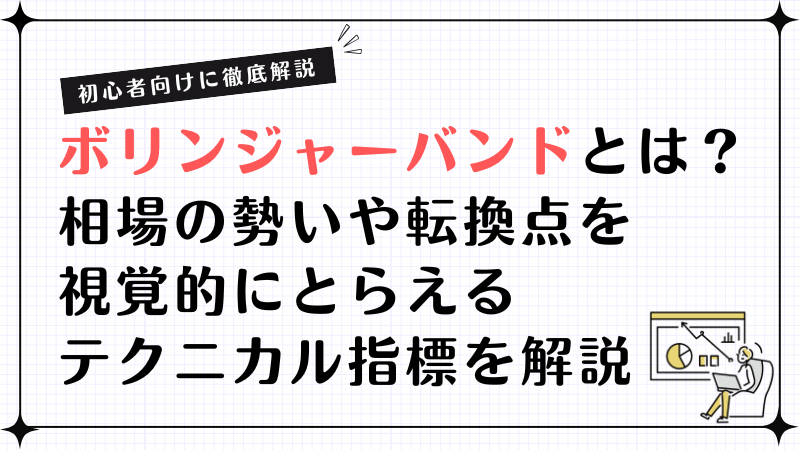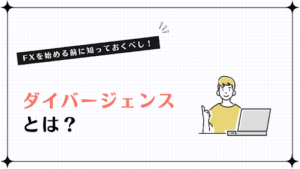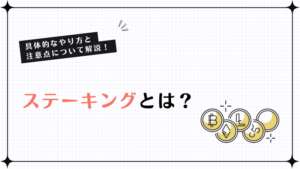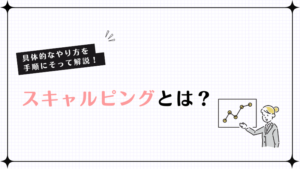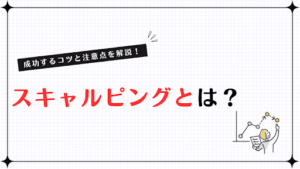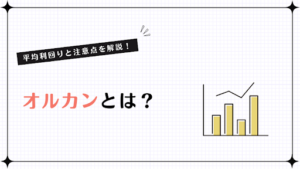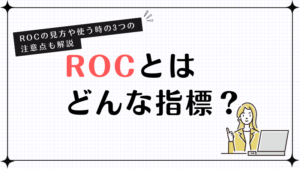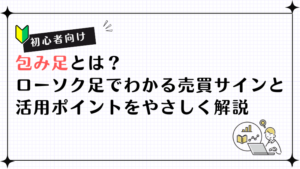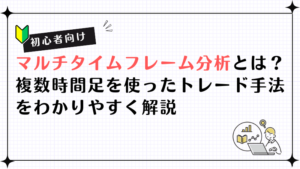テクニカル指標の「ボリンジャーバンド」は、相場分析には欠かせないツールです。
価格の動きを統計的に分析し、相場の勢いや転換点を視覚的にとらえられる、トレーダーにとって強力な味方となります。
統計的な裏付けがあり初心者にも扱いやすい指標として、多くのトレーダーから支持を集めています。
この記事では、ボリンジャーバンドの基本的な仕組みから実践的な活用法まで、わかりやすく解説します。
ボリンジャーバンドとは
この章を読むと以下のことが分かります。
- ボリンジャーバンドの基本的な仕組みと特徴が理解できる
- 相場分析における統計的指標の重要性が分かる
- トレーダーがなぜこの指標を重視するのかが理解できる
ボリンジャーバンドは、相場の変動を統計的に分析し、トレードのタイミングを判断するための優れたツールとして、世界中のトレーダーに広く活用されています。
移動平均線+標準偏差をもとに構成されるバンド
ボリンジャーバンドは、移動平均線と標準偏差という統計的な指標をもとに描かれるテクニカル分析ツールです。
テクニカル分析は、過去の価格やボリュームなどの市場データをもとに、統計や数学的手法を用いて将来の相場動向を予測する分析手法です。
心理的な要因や市場の力学が価格に反映されるという考えに基づいています。
中心には一定期間の価格の平均を示す「移動平均線」があり、その上下に価格のばらつきを表す「標準偏差」を加減した2本のライン(バンド)が描かれます。
通常、±1σ・±2σ・±3σといった複数のバンドが表示され、価格がこの範囲内でどの位置にあるかを見ることで、相場の過熱感や反転の可能性を判断するための仕組みです。
上下のバンド幅が相場のボラティリティを示す
ボリンジャーバンドの大きな特徴は、バンドの幅が相場の「ボラティリティ(価格変動の大きさ)」を表している点です。
相場が大きく動いているときはバンドが広がり、逆に値動きが少ないときはバンドが狭まります。
この性質により、相場が静かな状態から急に動き出す「エネルギーの溜まり具合」や、加熱している状況を視覚的に判断することができます。
例えば、バンドが極端に狭くなった後に一気に広がる場合、トレンドが発生する兆しと考えられます。
バンドの広がり方や形を見ることで、相場の勢いを読み取るヒントになります。
トレンド相場・レンジ相場の両方で活用できる特徴
ボリンジャーバンドは、トレンド相場(価格が一方向に動く相場)とレンジ相場(一定の範囲で動く相場)の両方で活用できるのが魅力です。
トレンド相場では、価格がバンドの外側に張り付く動きが続くことで、強い上昇や下落の流れを把握できます。
一方で、レンジ相場では、価格が上下のバンドで反発しやすく、「逆張り」の判断材料としても使われます。
相場の状態に応じて使い分けることで、ボリンジャーバンドは柔軟な分析ツールとして機能します。
状況を見極めながら活用することで、売買タイミングの精度を高めることができます。
なぜボリンジャーバンドを使うのか
この章を読むと以下のことが分かります。
- なぜボリンジャーバンドが多くのトレーダーに支持されているのかが理解できる
- 統計的な根拠に基づいた分析方法について学べる
- 相場の勢いや転換点を視覚的に捉える方法が分かる
ボリンジャーバンドは、その独特な特徴から多くのトレーダーに支持されており、相場分析に欠かせないツールの一つとして広く認知されています。
相場の「上昇・下落の勢い」がバンド幅でわかる
ボリンジャーバンドは、価格の動きに合わせて上下に広がったり縮まったりする“帯”のような指標です。
このバンドの幅を見ることで、相場の勢いや変動の大きさが直感的にわかります。
例えば、バンドが大きく広がっているときは、価格が大きく動いている、つまりボラティリティが高い状態です。
逆に、バンドが縮んでいるときは、相場が落ち着いており、大きな動きが出る前触れとなることもあります。
バンドの変化を観察することで、今の相場に勢いがあるのか、それとも停滞しているのかを判断しやすくなります。
価格が±2σの範囲に収まる確率の高さ(統計的根拠)
ボリンジャーバンドは統計的な考え方に基づいて作られており、中心の移動平均線から上下に「標準偏差(σ)」を使ってバンドを描いています。
特に±2σの範囲には、理論上、価格のおよそ95%が収まるとされています。
つまり、価格がこの範囲の外に出た場合、それは“異常”な動きと考えることができ、反転やトレンドの加速を予測するヒントになります。
統計的な裏付けがあるため、感覚ではなく根拠を持った分析が可能になります。
これは初心者にとっても安心感をもって使えるポイントです。
「どこまで上がるか・下がるか」の目安が視覚的にとらえられる
ボリンジャーバンドを使うと、価格が今後どこまで上がりそうか、あるいはどこで止まりそうかといった”目安”が視覚的に見えるようになります。
バンドの上限や下限に近づいたときは、相場が一時的に行き過ぎているサインとも解釈できるでしょう。
これにより、「そろそろ反転するかもしれない」「ここを突破すれば大きく動くかもしれない」といった判断がしやすくなります。
難しい数値を使わず、チャートを見るだけで相場の限界点や加速のタイミングがつかめることから、初心者にも扱いやすいテクニカル指標と言えるのです。
σ(シグマ)の意味と基本的な使い方
この章を読むと以下のことが分かります。
- σ(シグマ)の基本的な概念と意味が理解できる
- 統計学的な観点からボリンジャーバンドの仕組みが分かる
- バンドの設定方法と実践的な活用法が学べる
ボリンジャーバンドで使われるσ(シグマ)の概念を理解することで、より正確な相場分析が可能になり、売買のタイミングを効果的に見極めることができます。
±1σ、±2σ、±3σの意味(それぞれ68.3%、95.4%、99.7%)
「σ(シグマ)」は標準偏差を表す記号で、価格のばらつき=変動の大きさを数値化したものです。
ボリンジャーバンドでは、移動平均線を中心にして上下に±1σ、±2σ、±3σといったバンドを描いていきます。
統計上、価格は±1σの範囲に約68.3%、±2σには約95.4%、±3σには約99.7%の確率で収まるとされています。これを踏まえると、±2σを超える動きが出たときは”かなり珍しい”動きと判断でき、相場の転換やトレンドの加速を予測する材料となります。
σの意味を理解することで、ボリンジャーバンドの活用に深みが出るのです。
基本は±2σを使うが、戦略に応じてカスタマイズ可能
一般的にボリンジャーバンドでは±2σを使うのが基本です。
なぜなら、±2σ内に価格の95%以上が収まるとされており、過去の動きと比較して「行き過ぎかどうか」を判断するにはちょうどよい幅だからです。
しかし、トレードスタイルによってはこの幅を調整することもあります。
たとえば、より敏感に反応を見たい場合は±1σを使うこともあり、逆に大きな動きにだけ注目したいときは±3σを使うこともあります。
使い方に正解はなく、自分の目的に合った設定を見つけることが大切です。まずは標準的な±2σから始めるのが無理のない選択です。
バンドにタッチした=すぐ反発ではないことに注意
ボリンジャーバンドを見て「価格がバンドの上限に触れたからそろそろ下がるだろう」と考えるのは危険です。
確かに、バンドの端にタッチした場合、反転することもありますが、それが必ず起きるわけではありません。
強いトレンドが出ている場面では、価格がバンドに沿って伸び続ける「バンドウォーク」という状態になることもあります。
そのため、バンドに触れた=すぐに反発、とは考えず、他のテクニカル指標や相場の流れと組み合わせて判断することが大切です。
過信せず、総合的に状況を見て判断する姿勢が成功につながります。
バンドの収縮と拡大:相場の転換や加速を見抜くポイント
この章を読むと以下のことが分かります。
- バンド幅の変化と相場の関係性が理解できる
- 相場の転換点を予測するポイントが分かる
- 大きな値動きの前触れを見抜く方法が学べる
ボリンジャーバンドのバンド幅の変化は、相場の転換点や大きな値動きの予兆を捉えるための重要なシグナルとなります。
バンドが狭まる(スクイーズ)=エネルギー蓄積状態
ボリンジャーバンドが徐々に狭まり、バンド幅が縮小する状態は「スクイーズ」と呼ばれます。
この現象は、相場の値動きが小さくなり、エネルギーが蓄積されている状態を示すものです。
しばらくの間、価格が一定の範囲で落ち着いて動いていると、やがてどちらかの方向に大きく動き出す可能性が高まるでしょう。
スクイーズは、ブレイクアウト(相場の抜け出し)の前兆として注目されることが多く、「静けさの後の嵐」とも言われます。
このような局面では、バンドが再び広がり始めるタイミングを見逃さないように注意深く観察する必要があります。
バンドが広がる(エクスパンション)=急変動が発生中
ボリンジャーバンドが大きく広がる状態は「エクスパンション」と呼ばれ、相場に急激な変化が起きていることを意味します。
これは、強い上昇や下落が発生し、価格の変動幅が大きくなっている状態です。
エクスパンションは、スクイーズの直後によく起こるため、相場の「静から動」への転換点とみなされます。
この時期は相場が勢いに乗って動くことが多いため、流れに乗ったトレード戦略が有効になることもあります。
ただし、変動が大きい分リスクも高まるため、無理なポジションは避け、ストップロスなどのリスク管理を徹底することが大切です。
バンドの状態から「静から動」「動から静」の転換を読む
ボリンジャーバンドの幅を見ることで、相場が「動き始めるタイミング」や「一段落するタイミング」を読み取ることができます。
バンドが狭くなるスクイーズは、動き出す前の準備段階であり、逆にバンドが広がってきたら、今まさに相場が動いているというサインです。
そして、一定期間のエクスパンションの後に再びバンドが縮小してきたら、動きが一服し、次の展開に備えるタイミングともいえます。
こうした「静と動の切り替え」を視覚的にとらえられるのが、ボリンジャーバンドの大きな特徴です。
相場のリズムを読むうえで、非常に有効な手がかりとなります。
バンドウォークとは?急上昇・急落時の特徴的な動き
この章を読むと以下のことが分かります。
- バンドウォークの定義と特徴が理解できる
- 強いトレンドの見分け方が分かる
- バンドウォーク発生時の適切な対応方法が学べる
ここからは、バンドウォークの具体的な特徴と、トレーディングにおける活用方法について詳しく解説していきます。
価格がバンドの外側(+2σや-2σ)に沿って推移する状態

バンドウォークとは、価格がボリンジャーバンドの外側、特に+2σや-2σのラインに沿って動き続ける状態を指します。
通常であれば、価格は±2σの範囲内に収まることが多いのですが、強いトレンドが発生すると、バンドの外側に“張り付く”ように動き続けることがあります。
これがバンドウォークです。
一時的な反発があっても、大きな方向性は変わらず、トレンドが継続している可能性が高いため、チャートの見方を誤らないように注意が必要です。
価格がバンドを超えたからといって、すぐに反転すると考えるのは危険です。
「売られすぎ・買われすぎ」ではなく強いトレンドのサイン
ボリンジャーバンドの+2σや-2σに価格が接近すると、「買われすぎ」「売られすぎ」と考えがちですが、バンドウォーク中はそれが必ずしも当てはまりません。
むしろ、それは強い上昇または下落トレンドが発生しているサインであり、その勢いに逆らうのはリスクが高いとされています。
特に初心者は、「バンドに触れた=反発する」という固定観念を持ちやすいため注意が必要です。
バンドウォークは、市場の方向性がはっきりしている局面に多く見られるため、その流れに乗ることを意識するのが重要です。
バンドウォーク中は逆張りせず、トレンドに順張りが基本
バンドウォーク中は、価格が明確なトレンドに沿って動いているため、逆方向に仕掛ける「逆張り」は非常に危険です。
例えば、上昇トレンドでバンドの上側に沿って価格が推移している場面では、「高すぎるから売ろう」と考えると、さらに価格が上がり損失を広げてしまう可能性があります。
そのため、こうした局面ではトレンドの流れに従って「順張り」を意識することが基本です。
無理に天井や底を狙うのではなく、勢いに乗るスタンスで取引を行うことで、より安定した判断ができるようになります。
ボリンジャーバンドの活用例(初級〜中級)
この章を読むと以下のことが分かります。
- ボリンジャーバンドを使った具体的なトレード手法が理解できる
- トレンド相場とレンジ相場での活用法の違いが分かる
- エントリー・決済のポイントを実践的に学べる
ここでは、ボリンジャーバンドを使った具体的なトレード手法について、初心者でも実践しやすい例を順を追って解説していきます。
トレンド相場での順張りエントリー例
強いトレンドが発生している相場では、ボリンジャーバンドを使った「順張り」が有効です。
例えば、価格がバンドの上側(+2σ付近)に沿って上昇している場面では、トレンドが継続しているサインと捉えることができます。
このときは「押し目買い」を狙い、価格が移動平均線や+1σあたりまで一時的に戻ったタイミングでエントリーすると、無理のない形で上昇に乗ることが可能です。
バンドの傾きが右肩上がりで、出来高も伴っている場合は、より信頼度が高まります。
トレンドに逆らわず、流れに沿った形でポジションをとるのが、安定した成果につながります。
レンジ相場での逆張り活用例
相場が一定の範囲内で上下に動く「レンジ相場」では、ボリンジャーバンドの上下限を目安にした逆張り戦略が有効です。
例えば、価格がバンドの下限(-2σ)に近づいたら「売られすぎ」と判断し、反発を見込んで買いエントリーを検討します。
逆に、バンドの上限(+2σ)に近づいた場合は「買われすぎ」と考えて売りを狙うのが基本です。
ただし、相場に明確なトレンドが出ているときにはこの手法は機能しにくいため、バンドの幅が横ばいで安定しているかどうかを確認することが大切です。
過度な期待を避け、慎重なエントリーを心がけましょう。
バンドウォークからのエントリー注意点
バンドウォークが発生しているときは、相場に強いトレンドが出ているため、勢いに乗ってエントリーしたくなる場面です。
しかし、このタイミングでのエントリーは「飛び乗り」になりやすく、反転のリスクもあるため注意が必要です。
例えば、すでに何本ものローソク足が+2σや-2σ付近に張り付いている状態では、そろそろ一服する可能性もあります。
バンドウォーク中にエントリーする場合は、押し目や戻りを待って、移動平均線や+1σ付近で再び動き出すタイミングを狙うとリスクを抑えやすくなります。
焦らず、流れの中で最適なタイミングを見極めることが重要です。
まとめ
ボリンジャーバンドは、相場の動きを統計的な観点から視覚化する優れたテクニカル指標です。
移動平均線と標準偏差を組み合わせることで、相場のボラティリティや方向性を直感的に把握することができます。
初心者にとっては、バンドの幅や価格の位置関係から、相場の状態を理解しやすいツールといえます。
ただし、ボリンジャーバンドは万能ではありません。
トレンド相場とレンジ相場で使い方を変える必要があり、特にバンドウォーク時の判断には注意が必要です。
他のテクニカル指標や出来高なども併用しながら、総合的な判断を心がけることが重要です。
相場の「静と動」のリズムを捉え、適切なタイミングでエントリー・決済を行うことができれば、ボリンジャーバンドは非常に有効な分析ツールとなるでしょう。
ボリンジャーバンドの最強手法!利益を生む最強設定と組み合わせを徹底解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。