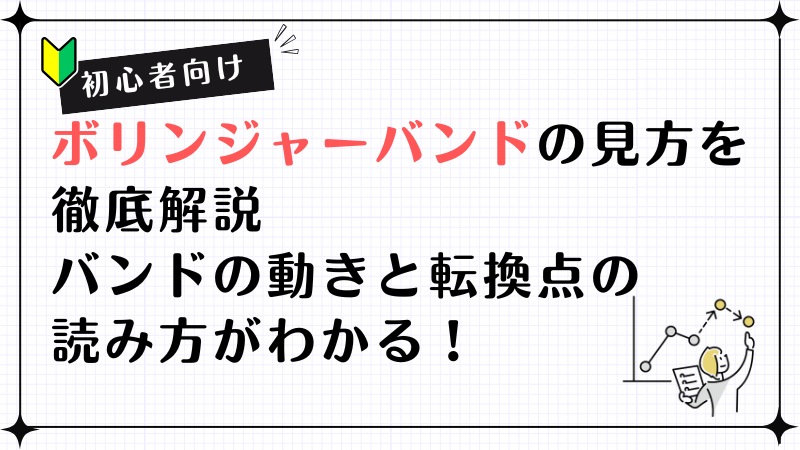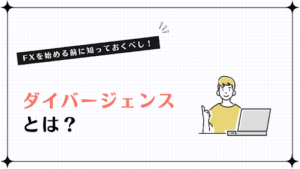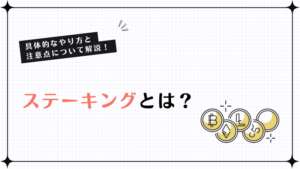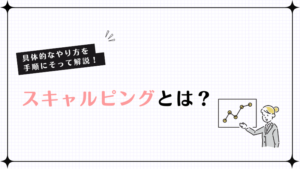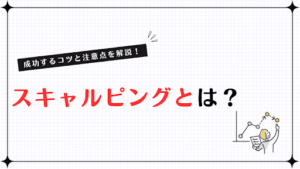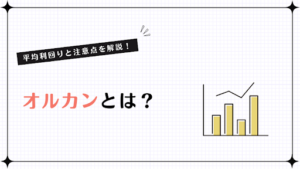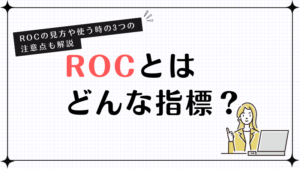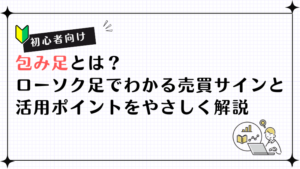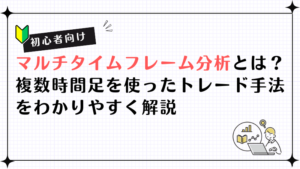ボリンジャーバンドを表示してみたものの、「±2σに触れたら反転?」「バンドが広がったり縮んだりするのは何の合図?」と、見方があいまいなまま眺めていませんか。
実はボリンジャーバンドは“当てにいく道具”というより、相場が今どんな環境にあるかを判断するための補助線です。
本記事では、中心線とバンドの意味、スクイーズと拡大、バンドウォーク、レンジでの見方などをわかりやすく解説します。
ボリンジャーバンドの基本構造
ボリンジャーバンドは、株式市場や為替市場など、あらゆる金融市場で活用されている強力なテクニカル指標です。
以下では、このツールの基本的な構造と特徴について詳しく解説していきます。
中心線(移動平均線)と上下のバンド(±σ)の関係

ボリンジャーバンドは、真ん中にある1本の線(移動平均線)と、その上下に広がる2本の線(バンド)で構成されています。
中心線は「最近の価格の平均的な動き」を表していて、過去の価格をもとに算出されています。
そしてその上下にあるバンドは、価格のゆれ具合に応じて広がったり縮んだりします。
価格が安定していればバンドは狭くなり、動きが激しければ広がります。
このように、中心線とバンドの関係を見ることで、今の価格が「普通の範囲内」なのか、それとも「めずらしい動き」なのかを判断できます。
多くの場合、価格は±2σの範囲内に収まる(約95%)
ボリンジャーバンドでは、上下のバンドの幅に「±2σ(プラスマイナス2シグマ)」という基準がよく使われています。
これは、過去の価格の動きをもとに、ほとんどの価格がその範囲内に収まる性質を示すものです。
具体的には、約95%の確率で価格が上下のバンドの間にあるとされており、逆にいえば、それを大きく超える動きが出たときには、何か特別な理由や勢いがある可能性が考えられます。
この「範囲の感覚」を持つことで、相場の異常な動きにも気づきやすくなるでしょう。
見方=どの位置に価格があるかを読み取る力
ボリンジャーバンドの使い方の基本は、「今の価格がバンドのどのあたりにあるか」を読み取ることです。
例えば、価格が上のバンドに近づいていれば「高くなってきている」、下のバンドに近づいていれば「安くなってきている」と判断できます。
さらに、バンドを突き抜けるような動きが出れば、「相場の勢いが強まっている」サインと考えることもできます。
重要なのは、価格の「位置」を見て、今の相場が普通かどうかを冷静に読み取る力を身につけることです。
ボリンジャーバンドの見方①|バンドの収縮と拡大を読む
ボリンジャーバンドの収縮と拡大は、相場の状態を理解する上で重要な指標となり、今後の値動きを予測するためのヒントを与えてくれます。
バンドの収縮(スクイーズ)=エネルギーの蓄積状態

バンドの収縮とは、ボリンジャーバンドの上下の幅がぎゅっと狭くなっている状態を指します。
このとき、価格の動きは小さく、静かな相場が続いていることが多いです。
しかし実は、この「静けさ」はエネルギーがたまっているサインでもあります。
例えるなら、ばねをギュッと縮めているような状態で、いつかどちらかに大きく動く可能性があります。
このような状況を「スクイーズ」と呼び、次に起こる大きな動きを予測するヒントになります。
静かなチャートを見たときこそ、その後の変化に備えておくことが大切です。
バンドの拡大(エクスパンション)=相場が動き出したサイン

バンドの拡大とは、上下のバンドの幅が大きく広がることを意味する「エクスパンション」と呼ばれる現象です。
これは価格が急に動き出したときに起こります。
価格が一気に上昇したり下落したりすると、バンドもそれに合わせて大きく広がり、相場に強い勢いが出ていることを示唆します。
収縮の後に拡大が起きると、大きなトレンドの始まりになることも多いため、バンドの動きに注目することでタイミングをつかむ手がかりとなるでしょう。
チャートの静寂と爆発を予測する見方のポイント
ボリンジャーバンドでは、「静かなとき」と「大きく動くとき」の変化に注目することが大切です。
バンドが収縮していれば、相場は一時的に落ち着いているように見えますが、その裏では次の大きな動きが近づいているかもしれません。
逆に、バンドが広がりはじめたら、実際にその動きがスタートしている可能性があります。
こうした変化の「前触れ」を見逃さずにとらえることが、ボリンジャーバンドの活用のコツです。
動きの「静」と「動」を意識して、チャートを読む力を育てましょう。
ボリンジャーバンドの見方②|バンドウォークでトレンドの強さをつかむ
バンドウォークは、トレンドの強さを視覚的に確認できる重要な現象で、相場の方向性を見極める上で欠かせないシグナルとなります。
急上昇・急落時に見られる「バンドウォーク」とは?

「バンドウォーク」とは、価格がボリンジャーバンドの上側または下側の線に沿って、しばらくの間ずっと動き続ける状態のことをいいます。
例えば、価格がバンドの上側に沿って上昇し続けていれば、強い上昇トレンドが発生している可能性が高いです。
逆に、下側に沿って動く場合は強い下落トレンドを示します。
この状態では、通常よりも勢いがあるため、ただの一時的な動きとは異なります。
バンドウォークが始まったら、相場に大きな力が働いている証拠として注目することが大切です。
ローソク足が±2σに沿って推移=強いトレンド中
価格がローソク足で表されるチャートで、±2σ(バンドの上端や下端)に沿って動き続けているとき、それは「強いトレンドが出ている」と考えられます。
上の線に沿っていれば上昇トレンド、下の線に沿っていれば下降トレンドです。
多くの人が「バンドの外に出たらそろそろ戻るのでは?」と考えがちですが、トレンドが強いときは、そのまま長く進むことがよくあります。
このような動きを見逃さないことで、トレンドにうまく乗るチャンスをつかむことができます。
「買われすぎ・売られすぎ」と誤認せず、順張りの判断材料に
ボリンジャーバンドの上側に価格が近づくと、「もう上がりすぎでは?」と感じるかもしれませんが、強いトレンドが出ているときには、そこからさらに上昇するケースも多いです。
これを「買われすぎ」と誤解して逆に売ってしまうと、トレンドに逆らって損をすることがあります。
バンドウォーク中は、無理に逆張り(流れに逆らった売買)をせず、流れに乗る「順張り」の判断材料として使うことが大切です。
勢いのある相場では、流れに乗る意識が重要です。
ボリンジャーバンドの見方③|転換点での逆張りを視覚的にとらえる
転換点の読み方を理解することで、相場の流れの変化を素早く察知し、新たな取引機会を見出すことができます。
価格が±2σを一瞬抜けて戻る動き=反転のサイン
ボリンジャーバンドの上や下の線(±2σ)を、価格が一瞬だけ飛び出してすぐに戻るような動きは、相場が「行き過ぎた」ときに見られる特徴的なパターンです。
このような動きが出たとき、「そろそろ流れが変わるかもしれない」と予想する人が多く、反転のサインと考えられます。
ただし、完全に戻る前に判断するのは危険なので、バンドの外に出てからしっかり戻ったことを確認するのがポイントです。
視覚的にわかりやすいため、初心者でも反転の兆しをつかみやすい場面です。
レンジ相場での逆張り戦略に使いやすい
レンジ相場とは、価格が一定の範囲内を行ったり来たりしている状態のことです。
このような状況では、上のバンドに近づいたら売り、下のバンドに近づいたら買い、という「逆張り」の戦略が効果的です。
ボリンジャーバンドは、このレンジ内の動きを視覚的にとらえやすいため、逆張りのタイミングを見極めるのに役立ちます。
ただし、レンジ相場かトレンド相場かを見分けることが前提で、トレンドが出ているときに逆張りすると失敗しやすいため注意が必要です。
見方に慣れるためのチェックポイントと注意点
ボリンジャーバンドを実践的に活用するために、以下のポイントを意識しながらチャートを見ていきましょう。
ボリンジャーバンドの誤解:「±2σに触れたら必ず反転」はNG
ボリンジャーバンドを見るときによくある誤解が、「±2σの線に価格が触れたら、すぐに反転する」という思い込みです。
たしかに反転することもありますが、実際にはそのまま勢いよくバンドに沿って進み続ける「バンドウォーク」になるケースも多くあります。
特に強いトレンドが出ているときは、何度もバンドに触れながら上昇・下降が続きます。
そのため、±2σに触れたことだけで反転と決めつけるのは危険です。
バンドの位置だけでなく、全体の流れや他の要素も合わせて判断することが大切です。
出来高やローソク足の形も合わせて判断する
ボリンジャーバンドだけで売買の判断をすると、だましに引っかかる可能性があります。
そこで注目したいのが、出来高(取引量)やローソク足の形です。
例えば、価格がバンドに触れたときに出来高が急に増えていれば、市場の注目度が高く、動きに勢いがあるサインと考えられます。
また、ローソク足がヒゲの長いピンバーや包み足のような形になっていれば、反転の兆しとして信頼度が上がります。
ボリンジャーバンドとあわせて他の情報も見ることで、より正確な判断ができるようになります。
バンドの端をタッチして戻る形に注目(例:ピンバーや包み足)
価格がボリンジャーバンドの上端や下端に触れたあと、すぐに戻るような動きは、反転のヒントになります。
特に、ローソク足の形が「ピンバー(長いヒゲが目立つ形)」や「包み足(前の足を包み込むような大きな足)」になっていると、買いや売りの勢いが変わり始めている可能性があります。
バンドだけで判断するのではなく、ローソク足の形まで確認することで、反転のサインをより明確につかむことが可能です。
視覚的にわかりやすいため、初心者にも取り入れやすい判断材料です。
ボリンジャーバンドが機能しやすい相場
ボリンジャーバンドは、すべての相場で同じように機能するわけではなく、値動きの特徴がある程度落ち着いている局面で、その読み取りがしやすくなります。
とくに、次のような相場環境では、バンドが示す情報を整理しやすい傾向があります。
まず代表的なのが、レンジ相場(値幅が一定の状態)です。
価格が一定の範囲内で上下を繰り返している局面では、ボリンジャーバンドの上下が「目安となる枠」として意識されやすくなります。
価格が上のバンド付近で伸び悩み、下のバンド付近で下げ止まりやすいなど、相場の動きがバンドの中に収まりやすいため、全体の状況を視覚的に把握しやすくなります。
次に、ボラティリティ(値動きの大きさ)が安定している局面も、ボリンジャーバンドと相性のよい環境です。
急激な上下動が少なく、日々の値動きがある程度そろっていると、バンド幅も極端に広がったり縮んだりしにくくなります。
このような状態では、現在の価格が「相場の中でどの位置にあるのか」を落ち着いて確認しやすくなります。
さらに、バンド幅が一定のリズムで推移している状態も重要なポイントです。
バンドが急に広がったり狭くなったりせず、一定の幅を保ちながら推移している場合、相場の環境が大きく変化していないことを示しています。
このようなときは、ボリンジャーバンドが示す「価格の位置」と「値動きの広がり」を、比較的安定した前提で読み取ることができます。
このように、ボリンジャーバンドは値動きが落ち着き、相場のリズムが整っている場面でこそ、相場環境を整理する補助線として機能しやすくなります。
まずは「今の相場がこの条件に近いかどうか」を確認することが、ボリンジャーバンドを正しく見るための第一歩になります。
よくある質問(Q&A)
Q1. ボリンジャーバンドは基本的に±何σを見ればいいですか?
A. 多くのチャートでは±2σが標準として使われることが多く、まずはそこから始めると整理しやすいです。
σを増減するとバンドの“広さの感覚”が変わるため、最初は設定をいじるよりも、バンド幅の変化(収縮・拡大)と中心線との距離に慣れる方が理解が早くなります。
Q2. ±2σに触れたのに、反転しないのはなぜですか?
A. 反転しないケースは珍しくありません。
バンドに沿って進むバンドウォークのように、相場の勢いが強い環境では、平均へ戻るよりも外側に張り付く動きが続くことがあります。
触れた事実だけでなく、バンド幅が拡大しているか、中心線から離れた状態が続いているか、といった“環境”までセットで見ると納得しやすくなります。
Q3. スクイーズが出たら、必ず大きく動きますか?
A. 大きく動くこともありますが、スクイーズは「方向が未決定になりやすい状態」を示すもので、動きの大きさや方向を約束するものではありません。
スクイーズを見たら「相場が静かで、次の変化に備える局面かもしれない」と整理し、拡大が始まった後の値動きの特徴を観察する方がブレにくいです。
まとめ
ボリンジャーバンドは、相場の動きを視覚的に理解するための優れたツールです。
中心線(移動平均線)と上下のバンド(±2σ)の関係を理解し、価格がどの位置にあるかを読み取ることで、相場の状況を把握できます。
トレンド相場では「バンドウォーク」に注目して順張りのタイミングを、レンジ相場では「バンドの端での反転」に注目して逆張りのタイミングを探ることができます。
ただし、バンドだけでなく、出来高やローソク足などの他の指標と組み合わせて総合的に判断することが重要です。
これらの基本を押さえながら実際のチャートで練習を重ねることで、より正確な相場判断が可能になるでしょう。
【初心者向け】ボリンジャーバンドの設定方法|期間・σの意味と最適な使い方を解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。