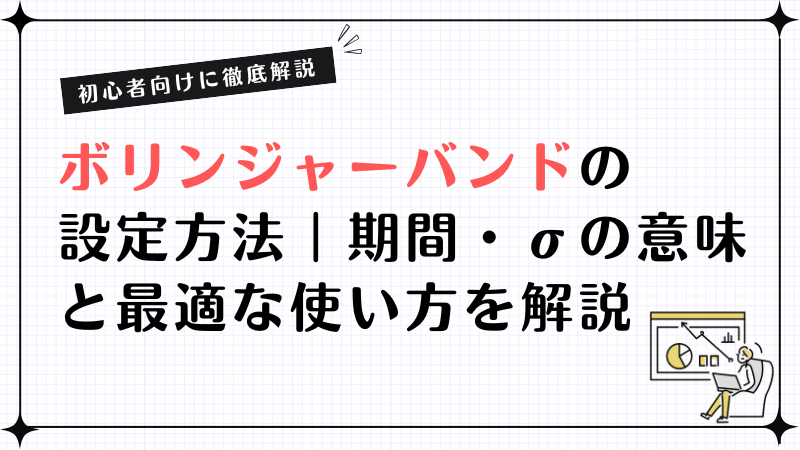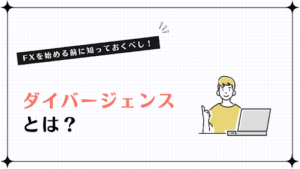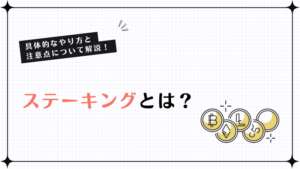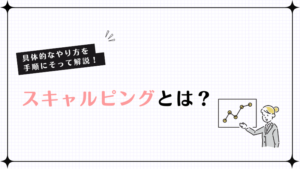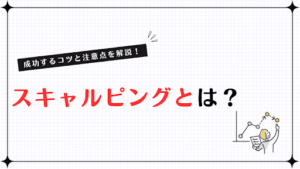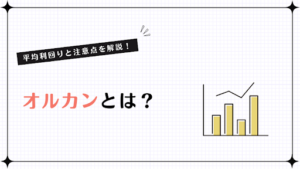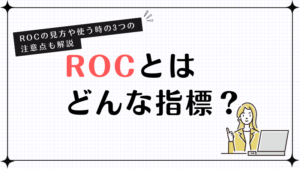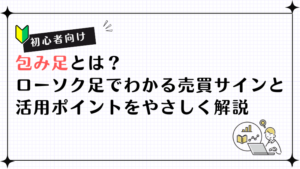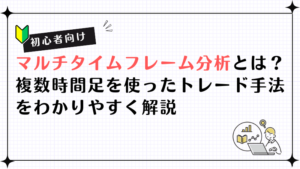ボリンジャーバンドをチャートに表示してはいるものの、「期間はこのままでいいの?」「±1σ・±2σって結局どれが正解?」とモヤモヤしていないでしょうか。
デフォルト設定のまま使い続けるのも一つの方法ですが、自分のトレードスタイルと合っていないと、シグナルを見誤ったり、無駄な売買が増えてしまうこともあります。
本記事では、ボリンジャーバンドの設定方法と考え方を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
ボリンジャーバンドとは?

相場のトレンドや価格変動を視覚的に理解できるボリンジャーバンドは、トレーダーにとって重要な分析ツールとなっています。
その基本的な仕組みと特徴を見ていきましょう。
移動平均線+標準偏差で構成されるテクニカル指標
ボリンジャーバンドは、移動平均線に標準偏差を加えた3本の線で構成されるテクニカル指標です。
中央にあるのが「移動平均線」、その上下にある2本の線は、価格の変動幅(=標準偏差)をもとに計算されます。
一般的には、上下のバンドが±1σ、±2σ、±3σのように設定されることが多く、現在の価格が過去の平均からどの程度離れているかを視覚的に捉えられます。
ボリンジャーバンドは相場のボラティリティ(価格の振れ幅)を測るのに役立ち、売買の判断材料として多くのトレーダーが活用しています。
価格の動きを“バンド幅”で視覚的に捉えるしくみ
ボリンジャーバンドの特徴は、相場の値動きを“バンド幅”で視覚的に捉えられる点です。
価格が大きく動いているときはバンド幅が広がり、動きが小さいときはバンド幅が縮まります。
これにより、現在の相場が活発か静かなのかを一目で把握できます。
さらに、価格がバンドの上限や下限に接近したとき、「買われすぎ」「売られすぎ」のサインとして注目されることがあります。
ただし、ボリンジャーバンドはあくまで“目安”であり、必ずしも反転を示すわけではありません。
視覚的な情報として、相場の勢いや転換の可能性を考える材料になります。
ボリンジャーバンドの「設定」とは何を意味する?
ボリンジャーバンドの「設定」は、このテクニカル指標の感度や使い方を決定づける重要な要素です。
適切な設定を選ぶことで、より効果的な相場分析が可能になります。
設定できる主な項目(期間・σなど)
ボリンジャーバンドには、主に「期間」と「σ(シグマ)」という2つの設定項目があります。
「期間」は移動平均線を計算するための過去のローソク足の本数を意味し、一般的には20期間(例:20日、20時間など)が標準です。
「σ」は標準偏差の倍率で、バンドの広がり方に影響を与える要素となります。
通常は±2σが使われ、これは価格が約95%の確率でその範囲内に収まるとされています。
設定を変更することで、感度の高い分析や長期的なトレンド判断など、目的に応じたカスタマイズが可能です。
トレードスタイル(短期・中期・長期)に合った設定を選ぶことが、正確な売買判断の第一歩となるでしょう。
チャートに与える影響と設定値の役割
ボリンジャーバンドの設定値は、チャートの見え方や売買判断に大きく影響します。
「期間」を短くすれば、バンドは価格の変化に素早く反応し、短期的な売買シグナルを捉えやすくなります。
反対に期間を長くすれば、バンドはより滑らかになり、中長期のトレンドを把握しやすくなります。
また、「σ」の値を小さく設定すればバンドは狭くなり、シグナルが頻繁に出やすくなりますが、ダマシも増えがちです。
一方でσの値を大きくすれば、バンドは広がり、信頼性の高いシグナルが得られやすくなります。
自分のトレード目的や分析スタイルに応じて、適切な設定を見極めることが、ボリンジャーバンドを活用するうえで欠かせません。
σ(シグマ)の意味と使い方をわかりやすく解説
相場分析において重要な役割を果たすσ(シグマ)の概念について、その基本的な意味から実践的な活用方法まで、順を追って解説していきます。
σ(標準偏差)とは?初心者にもわかる統計的な考え方
σ(シグマ)は、統計で使われる「標準偏差」を示す記号で、データのばらつきを表す指標です。
ボリンジャーバンドでは、価格の変動幅がどのくらいあるかを示すために使われます。
簡単にいうと、ある一定期間の平均価格から、実際の価格がどれだけ離れているかを数値化したものです。
価格の変動が小さいとσは小さくなり、バンドが狭まります。
逆に大きく動いているとσも大きくなり、バンドが広がります。
このように、σを使うことで、今の相場が静かなのか活発なのかを視覚的に理解できます。
±1σ、±2σ、±3σの違いと価格が収まる確率
ボリンジャーバンドで使われる±1σ、±2σ、±3σは、それぞれ価格がバンド内に収まる確率の目安を示しています。
±1σの範囲には価格が約68.3%の確率で収まり、±2σでは約95.4%、±3σではおよそ99.7%となります。
つまり、±2σを設定した場合、価格がほとんどその範囲内で推移することが期待されるため、バンドの外に出たときは“異常”な動きであると捉えられます。
このように、σの倍率によって「通常の価格変動」と「例外的な動き」の区別が可能です。
特に±2σは過剰反応や相場の転換点を見極めるサインとして活用されやすく、トレード判断の基準として幅広いトレーダーに支持されています。
なぜ±2σがデフォルトで使われるのか?
ボリンジャーバンドでは、多くのチャートツールで±2σが初期設定となっているのが一般的です。
その理由は、±2σの範囲に価格が約95%の確率で収まるとされ、適度な信頼性と使いやすさのバランスが取れているためです。
±1σではシグナルが多すぎてダマシが増えやすく、±3σでは逆にバンドの外に出る機会が少なくなり、売買のタイミングを見逃してしまう可能性があります。
±2σはこの両者の中間でありながら、適度な頻度でシグナルを提供し、なおかつ統計的な裏付けがしっかりしているため、初心者から上級者まで幅広く支持されています。
設定を変える前に、まずは±2σでバンドの動きに慣れることが重要です。
σを変えるとトレードにどんな影響があるのか(活用シーン別:短期/中長期)
σの設定値を変えると、バンドの幅が広がったり狭まったりし、それによってシグナルの出方も変わってきます。
例えば短期トレードでは、±1σや±1.5σといった狭めの設定にすることで、素早く反応しやすいシグナルが得られる反面、ノイズも増えやすくなります。
スキャルピングやデイトレードでは、この感度の高さが有利に働くこともあります。
一方で、中長期のトレードでは、±2σや±2.5σのように広めの設定にすることで、信頼性の高いシグナルを得ることができ、長いトレンドに乗る判断材料となります。
σをどう設定するかによって、売買タイミングやリスク管理の方針が大きく変わるため、自分のトレードスタイルに合わせて最適な設定を探ることが成功のカギです。
目的別・スタイル別に見るおすすめの設定値
ここでは、トレーダーのスキルレベルやトレーディングスタイルに応じた、具体的なボリンジャーバンドの設定値とその活用方法について詳しく解説していきます。
初心者におすすめの基本設定(例:期間20、±2σ)
ボリンジャーバンドを初めて使う方には、「期間20・±2σ」の設定が最もおすすめです。
この設定は多くのチャートツールでデフォルトとして採用されており、過去20本のローソク足をもとに移動平均線と標準偏差を算出します。
±2σは価格が約95%の確率でバンド内に収まる範囲を表しており、売られすぎ・買われすぎの判断材料として非常に使いやすいバランスのとれた設定です。
複雑な調整をすることなく、相場の勢いやトレンド転換の兆しを視覚的に捉えることができます。
まずはこの基本設定でチャートに慣れ、ボリンジャーバンドがどのように価格の変化を示しているかを理解するところから始めると、無理なく実践的な活用へつなげることができます。
スキャルピング・デイトレード向けの設定例
短期売買を中心とするスキャルピングやデイトレードでは、より敏感に価格の動きを捉える必要があります。
そのため「期間10・±1σ」や「期間12・±1.5σ」などの短期間・狭バンドの設定がよく使われます。
期間が短くなると、ボリンジャーバンドは価格の動きに対して俊敏に反応するようになり、小さな値幅でもエントリーポイントやイグジットポイントを細かく捉えることが可能です。
ただし、反応が速い分、ダマシも多くなるため、他のテクニカル指標(例:RSIや出来高)と組み合わせて使うことで、精度を高めることが重要です。
スキャルピングやデイトレードでは、スピード感とリスク管理のバランスが求められるため、ボリンジャーバンドの設定も戦略に応じて柔軟に調整することが効果的です。
スイングトレード・長期投資向けの設定例
数日から数週間、あるいは数カ月単位でポジションを保有するスイングトレードや長期投資では、ノイズを減らし、より大きなトレンドを捉えることが重要です。
そのためには「期間25〜30・±2σ〜±2.5σ」といった、期間をやや長く設定し、標準偏差の幅も広めにとる設定が適しています。
バンドが滑らかになることで、短期的な値動きに惑わされず、大局的な価格の流れを判断しやすくなります。
また、バンドが収束から拡大に転じたタイミングでトレンド発生を読み取るなど、方向性を重視したエントリーに役立ちます。
長期投資では、バンド外への乖離が起こった場合でも即時売買せず、ファンダメンタルズや経済動向とあわせて総合的に判断する視点も大切です。
設定を変える際の注意点とチェックポイント
ボリンジャーバンドの設定を変更する際は、トレードスタイルや市場環境に応じて慎重に判断する必要があります。
以下では、具体的な設定変更による影響と注意点について詳しく解説していきます。
期間やσを変えるとチャートの見え方がどう変わるか
ボリンジャーバンドの「期間」や「σ(シグマ)」の設定を変えると、チャートの見た目や売買シグナルの出方が大きく変わります。
例えば「期間」を短くすると、バンドが価格の動きに敏感に反応し、線が細かく上下するようになります。
短期トレードには便利ですが、ノイズも増えるため注意が必要です。
一方、「期間」を長くするとバンドはなめらかになり、大きな流れを捉えやすくなりますが、変化に気づくのが遅くなります。
また「σ」を小さく設定するとバンドが狭くなり、価格がバンドの外に出やすくなります。
これは売買のチャンスが増える一方で、ダマシのリスクも上がります。
反対にσを大きくするとバンドが広がり、強いトレンドのときにだけ反応するようになります。
設定によって分析の視点が変わるため、目的に応じた見方を身につけましょう。
「過剰最適化」にならないための考え方
ボリンジャーバンドを含むテクニカル指標は、設定を細かく変えながら最適な条件を探すことができますが、「過剰最適化」には注意が必要です。
過剰最適化とは、過去のチャートデータに合わせすぎて、実際のトレードではうまく機能しない状態のことを指します。
例えば、ある銘柄の過去5年分のチャートに対して、勝率が最も高くなる設定を探しても、将来の動きに対応できるとは限りません。
チャートは常に変化しているため、完璧な設定は存在しません。
重要なのは、安定的に機能する「汎用的な設定」を使いながら、トレードルール全体のバランスを保つことです。
設定変更はあくまで「調整」であり、無理に当てに行かず、長期的な視点で使いやすい設定を継続的に検証していく姿勢が大切です。
バックテストやデモトレードで検証する重要性
設定を変更した際には、いきなり本番トレードに使うのではなく、「バックテスト」や「デモトレード」で検証することが非常に重要です。
バックテストとは、過去のチャートに対して設定を当てはめ、どういった場面でシグナルが出たか、どのくらいの成果が出たかを確認する方法です。
これにより、その設定が有効に機能する相場環境やタイミングを客観的に把握できます。
また、実際にお金を使わずにリアルタイムの相場で試せるデモトレードもおすすめです。
心理的な負担が少なく、エントリーとエグジットの判断練習にもなります。
初心者ほど検証を重ねて、設定が自分のスタイルに合っているか確かめることが成功のカギとなります。
いきなり本番で使うのではなく、段階的に自信を持って使えるようにしましょう。
ボリンジャーバンド設定に関するQ&A
Q1. とりあえず「期間20・±2σ」にしておけば大丈夫ですか?
A. 初めて使う段階では、期間20・±2σは様子をつかみやすい設定です。
多くのチャートツールでも標準になっているため、解説書や他の情報とも照らし合わせやすいというメリットがあります。
ただし、どの設定にも得意・不得意があるので、「絶対にこれだけが正しい」というよりは、まずこの設定でバンドの動きに慣れながら、自分のスタイルに合うかをじっくり確認していくイメージが近いです。
Q2. 期間は何本くらいにするのが一般的ですか?
A. 日足であれば、20前後を一つの目安として使う人が多いです。
短期売買を重視する場合は10〜14など少し短めに、中期〜スイング寄りの場合は25〜30などやや長めにするケースもあります。
大事なのは「一般的だから」ではなく、自分が見ている時間軸や、どのくらいの速さで変化を捉えたいかに合っているかどうか、という観点です。
まとめ
ボリンジャーバンドは、価格の動きや市場の勢いを視覚的に把握できる非常に便利なテクニカル指標です。
設定値を変えることで、短期売買にも長期投資にも柔軟に対応でき、自分のトレードスタイルに合った分析が可能になります。
ただし、設定の調整には注意が必要で、検証を重ねることが成功への近道です。
まずは基本設定から始め、実際のチャートで動きを観察することで、より深く理解できるようになります。
学んだ知識を活かして、確かな判断力を身につけましょう。
ボリンジャーバンドの最強手法!利益を生む最強設定と組み合わせを徹底解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。